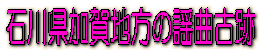
| №1 安宅の関所 〔小松市安宅町〕 |
|
|
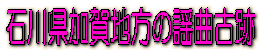
| №1 安宅の関所 〔小松市安宅町〕 |
|
|
|
№2 小松市の曳山子供歌舞伎 |
|
|
| 小松市の曳山子供歌舞伎・演目 |

私の住んでいる小松市では、曳山子供歌舞伎で町おこしをしています。勧進帳は謡曲「安宅」を元にして創られました。 |
| №3 実盛首洗池 〔加賀市手塚池〕 |

|
| №4 実盛塚 〔加賀市篠原新町〕 |

篠原古戦場の海岸よりにあるのが、この実盛塚です。高速片山津インターを出て右折し、汐見橋の信号を直進して、橋を渡って五百メートルの左側にあります。駐車場は右側にあります。 |
| №5 実盛の兜 〔小松市上本折町〕 |
 小松市内の上本折町に、延喜式内の古社「多太神社」があります。この神社に謡曲「実盛」の兜があります。高速小松インターを出て右折し、梯川を渡り信号を左折して市内に入ります。市内の真ん中の「京町」の交差点を右折し2キロ位、道が二股に分かれる左側に神社があります。  木曾義仲はここに詣でて、平家追討を祈願しました。合戦後「実盛の兜」をこの神社に寄進しました。兜は宝物殿のガラスの容器に収まっています。頼めば見せてもらえます。国の重要文化財に指定されていいます。  芭蕉は「奥の細道」の途中、この神社に立ち寄り「むざんやな 兜の下の きりぎりす」と詠みました。この句は謡曲「実盛」をふまえて詠まれています。境内に句碑があります。又「虫枯るる 宵を不覚の かがみぐせ」木隹(小松の人)などの句碑もあります。芭蕉の像も新しく建てられました。 |
| №6 多太神社の能舞台 〔小松市上本折町〕 |
|
|
| №7 鏡の池 〔加賀市深田町〕 |
|
尼御前岬から橋立魚港を過ぎ、北前船の里を通り、信号を「百万石時代村」の方へ曲がるとすぐ深田の村を通ります。村の入り口で左に入り百メートル、又左に入り百 |
| №8 歌占の滝 〔白山市鶴来町白山町〕 |
|
|
| №9 仏御前火葬の地 〔小松市原町〕 |
|
白山禅定を志す旅の僧が、加賀国仏の原の草庵で、仏御前の亡霊と出会うと言う謡曲「仏原」の舞台になっているのは、小松市の郊外の原町です。仏御前はこの町の出身です。 |
| №10 仏御前屋敷跡 〔小松市原町〕 |
|
|
| №11 仏御前の尊像 〔小松市原町〕 |
|
|
| №12 仏御前お産石 〔白山市吉野谷村木滑〕 |
|
|
| №13 井筒の井桁 〔金沢市卯辰山公園〕 |
|
|
| №14 熊坂長範出生地 〔加賀市熊坂町〕 |

熊坂長範の亡霊が長刀を振るい、無念の最期を語る謡曲「熊坂」の舞台は、岐阜県美濃の垂井町青野辺りで、長範物見の松などが残っています。 |
| №15 梅田の里 〔金沢市梅田町〕 |
|
|
| №16 鳴和の滝 〔金沢市鳴和町〕 |
 謡曲「安宅」の最後の場面、「これなる山水の、落ちて巌に響くこそ、鳴るは瀧の水」と出てきます。この瀧のあるのが金沢市鳴和町の「鹿島神社」の境内です。弁慶の舞った時代には、よほど水量が多い瀧だったのでしょう。弁慶が舞ったおかげで、この辺りの地名が「鳴和」となってしまいました。 謡曲「安宅」の最後の場面、「これなる山水の、落ちて巌に響くこそ、鳴るは瀧の水」と出てきます。この瀧のあるのが金沢市鳴和町の「鹿島神社」の境内です。弁慶の舞った時代には、よほど水量が多い瀧だったのでしょう。弁慶が舞ったおかげで、この辺りの地名が「鳴和」となってしまいました。鳴和の広い表通りの山側に、細い旧北陸道が走っています。この一方通行の道の途中の左に曲がる角に、「石川縣十名所義經旧蹟鳴和瀧」と書いた古い大きな案内の石柱があります。電柱の陰になっているので見にくい石柱です。左に折れ、突き当たりに鹿島神社があります。今は木樋よりチョロチョロと水が落ちています。どう見ても瀧には見えません。ちょっとがっかりします。車で行くと道は細く袋小路ですので気を付けてください。 |
| №17 弁慶の法螺貝 〔小松市安宅町〕 |
|
|
| №18 弁慶謝罪の地 〔能美市根上町道林町〕 |

安宅関から北へ四キロくらいの、道林町の道林寺跡に「弁慶謝罪の地」の碑が立っています。 |
| №19 尼御前岬 〔加賀市美岬町〕 |
|
|
| №20 岩根宮の義経通夜 〔能美市辰口町岩本〕 |

国道八号線から、寺井町より鶴来までの鶴来街道を行くと、手取川の天狗橋を渡る少し前に、岩本と言う村を通ります。村に入っていくと岩本神社に突き当たります。ここは昔は、白山比咩神社の三社〔金釼宮、別宮、岩根宮〕の一つ、岩根宮の址だそうです。昔は神仏一緒に拝んでいたので、ここには本尊十一面観音像が奉られていました。建物も、もっと多数ありました。 |
| №21 大野湊神社 〔金沢市寺中町〕 |

金沢市内より、金石に通ずる金石街道を行くと、左側の寺中町に「大野湊神社」があります。延喜式神名帳に載っている古社です。 |
| №22 大野湊神社の能舞台 〔金沢市寺中町〕 |
|
|
| №23 布市神社 〔野々市市本町〕 |
|
|
| №24 小松天満宮の能舞台 〔小松市天神町〕 |
|
|
| №25 フォルテの富樫像 〔野々市市本町〕 |
|
|
| №26 富樫館跡 〔野々市市本町〕 |

|
| №27 故郷の山・白山〔小松市木場潟より〕 |
|
|
| №28 故郷の河・手取川〔能美市美川町河口より〕 |
|
|
| №29 杜若の像〔金沢市石引四〕 |
|
|
| №30 義経腰掛石〔白山市鶴来町〕 |
|
|
| №31 金剣宮の能舞台〔白山市鶴来町〕 |
|
|
| №32 白山神社の能舞台〔加賀市山中温泉白山町〕 |
|
|
| №33 菅生石部神社の能舞台〔加賀市大聖寺菅生町〕 |
|
|
| №34 泉鏡花の瀧の白糸〔金沢市橋場町〕 |
|
|
| №35 宝生紫雪の墓〔金沢市東山〕 |
|
|
| №36 深谷温泉の能舞台〔金沢市深谷町〕 |
|
|
| №37 加賀の千代女〔白山市松任西新町〕 |
|
|
| №38 本光寺〔小松市本折町〕 |
|
謡曲「満仲」があります。観世流では同じ曲を謡曲「仲光」と言います。多田満仲は一子美女丸を僧にするために、中山寺に預けていますが、学問をしなく武勇ばかり好むので、仲光に命じて殺させます。主命とはいえ幼君を殺すことが出来ず、わが子を身代わりにします。シテ仲光の武士ととしての悲しみを描いた、少し毛色の変わった能です。 |
| №39 日吉神社〔小松市本折町〕 |
|
|
| №40 猿丸神社〔金沢市笠舞三丁目〕 |

百人一首に「奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声きく時ぞ秋は悲しき」があります。猿丸太夫の歌です。この平安初期の歌人は謎の人物らしいです。その存在すらあやしくて、柿本人麻呂と同一人物ではないかと言う説まで有るそうです。猿丸太夫の名は謡曲「草紙洗」のシテの言葉に出てきます。 立札に依れば、三十六歌仙の一人、猿丸太夫の旧房跡に、太夫を祭神として、千年前の平安時代に神社創立との事です。それにしても珍しい神社だと思います。犀川にかかる下菊橋を渡り、犀川大通りを右折してすぐ、レストラン・ガストの隣りの笠舞町にあります。この笠舞と言う地名は、旅に立つため庵を出、犀川のほとりで突風により、太夫の笠が舞い上がった事に由来しているのだそうです。 |
| №41 菟橋神社〔小松市浜田町〕 |
 小松市の中心を横切っている、空港・軽海線の道路沿いに、菟橋神社があります。本殿の左横に「牛若松」と呼ばれる高い松があります。謡曲「安宅」の、源義経一行が安宅関の無事通過を祈願して植えた、と言い伝えているそうです。この松の幹内部が空洞になっていて、神社が補強に乗り出したと新聞に載ったので、初めて「牛若松」を知りました。すぐ近くに住んでいながら、うかつにも初めてこの松を知りました。  さてこの菟橋神社に、松尾芭蕉もも訪れています。曾良旅日記によれば、7月27日、この日は折りよく、菟橋神社の祭礼の日でもあったので、ここに詣でてから山中温泉に向って旅立っています。この祭礼は現在の夏祭り・西瓜祭りなのでしょう。神社の鳥居前に「しほらしき名や小松吹く萩薄」の句碑があります。 |
| №42 松任運動公園舞台〔白山市松任倉光町〕 |
 松任市の国道八号線よりに、大きな運動公園があります。写真はその中にある野外の水上舞台です。ここで毎年薪能があります。なかなか雰囲気のある舞台です。 しかしここで薪能をするのは大変です。橋係りは狭いし、舞台はセメントでザラザラ、大掛かりな装置を作らねばなりません。何とかいい方法が無いものでしょうかね。 松任だけあって新作、謡曲「朝顔」が時々出ます。 |
| №43 若宮八幡宮の能舞台〔白山市松任若宮〕 |
 明治に入り、幕府というパトロンを失った金沢能楽界は絶滅の機におちいりますが、佐野吉之助を中心とする、お能好きの素人によってだんだんと復興に向かいます。明治33年(1900)に吉之助は自宅に「佐野舞台」立てました。翌年「金沢能楽会」が設立され、以後百年、一千百回に及ぶ定例能の歴史が始まりました。この舞台は白州が青天井で、天候の影響をうけ傷みが烈しく、昭和7年(1932)に金沢能楽堂として建て替えられました。この舞台が、市役所の拡張により移転したのが現在の県立能楽堂です。 さて最初の「佐野舞台」は松任市のここ「若宮八幡宮」に移築されました。しかし火事で焼失。今はありません。写真は境内にある松任出身の俳人「加賀の千代女」の像。 |
| №44 手折らじの館〔加賀市山中温泉〕 |
 謡曲「枕慈童」、観世流では「菊慈童」があります。誤って帝の枕をまたいた慈童は深山に流されます。流罪を哀れんだ帝は、枕に法華経の詞を書いて与え、その文句は菊の葉に写され、その葉に置く露が不老不死の薬となり、慈童は七百歳まで生きました。 謡曲「枕慈童」、観世流では「菊慈童」があります。誤って帝の枕をまたいた慈童は深山に流されます。流罪を哀れんだ帝は、枕に法華経の詞を書いて与え、その文句は菊の葉に写され、その葉に置く露が不老不死の薬となり、慈童は七百歳まで生きました。ここは山中温泉。芭蕉は奥の細道で、私の住んでいる小松から、この山中温泉に来ています。芭蕉は温泉を称える「温泉頌」を残しています。「皮肉うるほひ、筋骨に通りて、心神ゆるく、偏に顔色をとどむるここちす。彼の桃源も舟をうしなひ、慈童が菊の枝折りもしらず。ばせお 山中や 菊はたおらじ 湯のにほひ 元禄二仲秋日」  この句は奥の細道にも載っています。この句は謡曲「枕慈童」を踏まえています。慈童は菊の露を飲んで長寿を保ったが、山中温泉ではその必要も無いというもの。 写真は、川のほとりの「芭蕉堂」と、温泉街の中央に出来た、芭蕉資料館の「手折らじの館」の前に出来た芭蕉と曾良の石像です。二人はここで別れます。 |
| №45 都もどり地蔵〔加賀市八日市町〕 |
 動橋イブリバシより大聖寺へ抜ける県道の、JR線の上を高架橋で過ぎて1キロ位先の道の左側に、小さな石の祠に入った地蔵さんがあります。立て札によれば「歌人西行が、西住と共に諸国行脚の途中、大聖寺川上流の西住村に滞在し、その渓谷美を愛でた。やがて西行が都に帰るとき、都戻り橋という辺りで、別れたのがこの付近である。終生の師弟、西行と西住が、別れを惜しんだこの場所にいつしか地蔵が祀られ、人々はこれを都もどり地蔵と呼んだ」。そのとき西住法師が詠んだ歌「もろともに ながめながめて 秋の月 ひとりにならん ことぞかなしき」 鎌倉時代の歌人西行法師は、謡曲「西行桜」「遊行柳」などに名前が出てきます。 この地蔵さんのことは、金沢のT・M様よりメールにて教えて頂きました。ありがとうございました。又、西住の歌「もろともに 」は富山県呉西の7番に載せた西住塚では、同じ歌を西行の作としています。西住村の事は、判りましたら又載せます。 |
| №46 西住霊碑〔加賀市山中町市の谷〕 |
これも金沢のT・M様より教えて頂いた、西住の墓の写真です。探してきました。 都もどり地蔵の立て札に寄れば、西行法師は弟子の西住と諸国を行脚し、大聖寺川上流の西住村に滞在したとあります。大聖寺川を遡ると、山中温泉の鶴仙峡を過ぎ、我谷ダムに出ます。左折して新設の九谷ダムを過ぎ、九谷の村を左折して県民の森のほうへ走ります。なかなかの山奥です。やがて道の左に「福寿草の里」という施設があり、その左隣にこの墓があります。西住霊碑とあり側面にいわれが彫ってあります。汚れていてよく読めません。どうも富山県庄川町にある西住塚と同じ話のようです。詳しく判りましたらお知らせします。 |
| №47 江沼神社〔加賀市大聖寺八間道〕 |
 大河ドラマ「利家とまつ」は、金沢藩の初代藩主前田利家の話でしたが、三代藩主利常の三男利治が、支藩として出来た大聖寺藩の初代藩主になりました。以来大聖寺十万石は14代二百年間、金沢に劣らぬ発展を遂げました。14代藩主前田利鬯マエダトシカは最後の殿様で、大変お能が好きでした。210番全曲を舞ったとの事です。明治になり前田家は東京に出ましたが、東京でも舞台を造り、能楽師を集めてお能を舞い、能楽復興に力を尽くしました。大聖寺では、殿様の影響で今でも能楽が盛んです。正月二日に、利鬯殿様の写真を飾って、舞囃子をする「お松ばやし」が今でも続いています。 江沼神社は藩祖利治を祀ります。大聖寺藩は城を造らず、江沼神社の辺りに屋敷を構えていました。神社は昭和9年の大火で全部燃えましたが、写真の「長流亭」だけが残りました。3代藩主利直の休息所として作られたもので、重要文化財に指定されています。能舞台も有りましたが燃えてしまいました。神社所蔵のの能面能装束は市文化財に指定されています。境内には武家庭園も残っています。  また、「日本百名山」を書いた大聖寺の作家、深田久弥の文学碑もあります。 江沼神社は大聖寺駅より北1キロ位。錦城山公園のふもとにあります。 |
| №48 白山比咩神社〔白山市鶴来町〕 |
 全国に2,700社の末社を持つ白山神社の総本山。白山比咩神社は鶴来町に鎮座しています。わが故郷の山、霊峰白山を御神体とし、イザナギ・イザナミの神を祀っている古社です。白山は僧泰澄によって開山し、平安時代初期に参拝の禅頂道が開かれ、ここが加賀よりの登山の基地となりました。境内は、杉、桜の大樹が多く神域を保っています。古社にふさわしく社宝類も豊富です。謡曲の奉納額もあります。 全国に2,700社の末社を持つ白山神社の総本山。白山比咩神社は鶴来町に鎮座しています。わが故郷の山、霊峰白山を御神体とし、イザナギ・イザナミの神を祀っている古社です。白山は僧泰澄によって開山し、平安時代初期に参拝の禅頂道が開かれ、ここが加賀よりの登山の基地となりました。境内は、杉、桜の大樹が多く神域を保っています。古社にふさわしく社宝類も豊富です。謡曲の奉納額もあります。物の本によると、白山は謡曲の四曲に謡われるとありました。謡曲「藤」の道行。謡曲「歌占」の次第。謡曲「仏原」の次第道行、と見つけましたが、もう一曲が見つかりません。どなたか教えて下さい。  見知らぬ方より、メールであとの一曲を教えていただきました。謡曲「花筐」の後シテのサシの謡です。「物の本」とは、「謡曲ゆかりの古跡大成・木本誠二著」の事です。自分でろくに探しもせず、教えて頂きありがとうございました。 白山比咩神社の奥ノ院は「白山」です。社も頂上にあります。2010年の写真です。 |
| №49 弁慶の足跡〔小松市西尾地区松岡町〕 |
 小松市より国道416号線を、旧尾小屋鉱山に向かってドライブしていたら、西尾村布橋の国道傍の「十二ヶ滝」の上に、鯉のぼりが泳いでいました。  この村の右手の林道を少し入っていくと、「布橋の水芭蕉の群生地」があります。こんなところにも水芭蕉が咲くのですね。見頃でした。  十二ヶ滝の所の「西尾八景」の立て札に「弁慶の足跡」の字を見つけて探しに行きました。。布橋の先を左に折れて2キロほど行くと、松岡の集落を通ります。 ここの松岡大橋の辺の立て札に拠れば「松岡大橋の下の両岩の傍らに、巨人の足跡があり、弁慶がここを通った時、この岩から一跨ぎに向かい岸に渡ったので、岩に足跡がのこり弁慶岩と言われる」とあります。近くに象岩もあります。写真は橋の上より写したものです。謡曲「安宅」の主人公弁慶さんは、こんな所にも現れて、忙しいですね。  また集落の中に大きなしだれ桜が満開でした。「千恵子桜」と名称がつけてありました。どんないわれがあるのでしょうか。 名前の由来見つけました。ここに住んでいた千恵子さんが、ブラジル移住の時、記念に植えたのだそうです。 小松市内の自宅より30分で着きます。 |
| №50 全昌寺〔加賀市大聖寺神明町〕 |
 大聖寺の全昌寺は、奥の細道で芭蕉が泊まったお寺です。山中温泉で芭蕉と別れた曾良も前夜この寺に泊まり、「よもすがら秋風聞くやうらの山」と詠み、芭蕉も「庭掃いて出ばや寺に散る柳」と詠んでいます。 お寺は最近、山門が作られて立派に成りました。  芭蕉塚と曾良の句碑があり、芭蕉の泊まった部屋も再現されました。  またこの寺には極彩色の五百羅漢が全部そろった羅漢堂があります。縁があって、その内の一体を私が受け持っています。羅漢堂を建てる時、寄進者がわからなくなった像の整理をした時、大聖寺に住んでいる笛方の吉野師に頼まれて、太鼓方の私に、太鼓を打っている像を紹介してくれたものです。両手に撥を持っているのがそうです。 全昌寺は謡曲には関係ありませんが、お隣の正覚寺に、謡曲「祇王」や謡曲「仏原」の主人公の仏御前が、清盛から拝領し、故郷小松まで背負ってきた「履行弥陀如来」が伝わっているとの事。また仏御前の木像があるとの事です。 何時訪ねても、どなたも不在の、不思議なお寺です。 |
| №51 中村神社拝殿〔金沢市中村町〕 |
 金沢駅より南下し御影大橋を渡り、2百m先の信号を左折するとすぐ中村神社に突き当たります。ここの拝殿はこのたび「文化庁登録有形文化財」に指定されました。この拝殿は、旧金沢城の二の丸御殿にあった能舞台を移築したものだそうです。桃山風建築様式で総ケヤキ造り、四方の欄間には龍が彫られ、塗り格天井には極彩色の絵があしらわれ、金の金具が使われているとの事です。加賀百万石の歴代藩主が、居並ぶ家老を前に能を舞った光景がしのばれます。  この能楽堂は二の丸御殿に隣接して建てられた独立の建物で、白州を挟んだ御殿の座敷が見所でした。明治3年に明治維新で戦死した加賀藩武士を祀るため、卯辰山に「顕忠祠」を建てる事になり、明治維新で主を失ったこの能舞台が社殿として活用され移築されました。二の丸御殿はその後、明治14年の火災でことごとく焼失してしまい、金沢を見下ろす卯辰山に運命的に能舞台だけが残ることになりました。昭和10年「顕忠祠」は石川護国神社に合祀され、元能舞台はポツンと残され荒れるにまかされました。昭和40年、この中村神社の拝殿を建て替える話が持ち上がり、再び白羽の矢が立ったのが放置された元能舞台でした。 |
| №52 仏御前の子供地蔵〔小松市尾小屋町〕 |
 最近、里山歩きに熱中しているが、尾小屋の大倉岳の帰りに、「仏御前の子供地蔵」を見付けた。石碑由来に寄れば「この地蔵さんは、尾小屋トンネルの山端、旧道脇にありました。トンネルの上出口の川端に、大岩があったので(昭和九年の洪水で流失)、その辺りを大岩畑と呼ばれていた。この地蔵さんは、昔から子供の地蔵さんと伝わり、立派な祠に奉られて大岩畑に鎮座し、代々の地元衆に護られてきました。  その昔、平清盛に寵愛された白拍子の仏御前は、ここ大岩の所で清盛のの子を死産した由。それ故ここに、この地蔵さんを建立し、清盛との子供を懇ろに葬り弔った。産後の仏御前は長原村の中山家にお世話になり、別れに際し、深く信仰していた十一面観音像と、櫛と、こうがいをお礼品として旅立ったと云う。その品々は、現在中山家に手厚く所蔵されている由でございます。中山主人が、仏御前を見送った阿手坂峠は仏峠と云われている次第です。」 仏御前は、謡曲「仏原」「祇王」のシテです。この地蔵さんと石碑は、新しい尾小屋トンネルの小松側の入り口広場にあります。 |
| №53 景清池〔白山市 町〕 |
 「口三方岳」という1269mの山に、登りに行きました。白山市河内町のセイモアスキー場の先より登ります。3時間20分、ひたすらに登って、「景清池」に到着。6月の半ばなのに一面の雪渓でした。水が溶けたら池になる様です。この池は、平家の武将「悪七兵衛景清」の流した涙で出来た池だと云う伝説が残っているようです。 謡曲「景清」という名曲があります。能楽師の端くれとして、ぜひ一度訪れたいと思っていたので大満足です。同行のK君は再度の登山だが、まさか6月に雪に覆われているとは思わなかったらしい。どう見ても池には見えません。登山口の内尾の村に、平家の落人伝説が伝わっているようです。  謡曲「景清」の舞台は、九州宮崎の日向です。それなのに、なぜこんな、石川県の山の中に、景清の伝説があるのでしょうね。 翌年また「口三方岳」へ登りに行きました。今度は6月下旬です。新緑の中に大きな池が見えました。同じ6月なのに、年によって違うものですね。 |
| №54 小坂神社〔金沢市鳴和町〕 |
 里山歩きで、卯辰山から春日山を縦走して降りてきたら、この神社にたどり着いた。御祭神由緒を読むと、奈良の春日社の社領であり春日神を祀る。 境内社に「瀧波社」があり清滝権現を祀る。義経一行が奥州下向の折、弁慶がここで「鳴るは滝の水」の舞曲を奏した、と書いてある。 ここも鳴和町です。鳴和の滝も近いです。 |