| 第十一巻 當麻と吉野の能楽古跡 |
 喧窮会の仲間と、大和路の「當麻・葛城・吉野」方面へ、バスドライブです。まず訪れたのは、謡曲「當麻」ゆかりの“石光寺”です。中将姫と當麻寺の曼荼羅伝説によって創られた「當麻」は、仏教用語が多くて難しい曲です。ここ「石光寺」は、中将姫が蓮の糸で織ったという、糸を染めた井戸があるので、「染寺」とも呼ばれています。こじんまりとした素敵なお寺です。写真は井戸の上に建てたお堂です。  同じく謡曲「當麻」ゆかりの、すぐ近くの“當麻寺”です。写真の国宝の「本堂」に、中将姫が蓮の糸で織ったという曼荼羅がかかっています。本物は国宝で傷みが激しいので、室町時代に転写された、重要文化財の曼荼羅だそうです。 同じく謡曲「當麻」ゆかりの、すぐ近くの“當麻寺”です。写真の国宝の「本堂」に、中将姫が蓮の糸で織ったという曼荼羅がかかっています。本物は国宝で傷みが激しいので、室町時代に転写された、重要文化財の曼荼羅だそうです。當麻寺は何度来てもいいお寺です。牡丹でも有名ですが、私が一番最初に訪れた、桜の満開の時が一番印象的です。夜行で出かけて早朝に着き、西の三重塔の下で、持っていったおにぎりを食べていたら、桜吹雪が降り注ぎました。  當麻寺の“中之坊”の本堂です。中将姫はここで剃髪しました。裏に周ると、書院と素敵な庭園があります。  これより葛城の古道と呼ばれる、古代の道があった辺りを行きます。古社が色々在ります。ここは“九品寺”です。本堂から裏山にかけて、おびただしい石仏群が埋め尽くしています。 ここは“葛木坐一言主神社”です。謡曲「葛城」にゆかりの地です。一言の願いを叶えてくれる一言主は、葛城の神です。裏山の山地が葛城山です。 葛城の神は、役行者に岩屋に閉じ込められ、三熱の苦に苦しめられますが、山伏の祈祷で自由になり、喜びの大和舞を舞います。 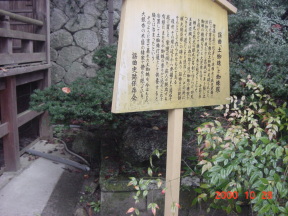 同じ一言主神社の境内に、謡曲「土蜘」にゆかりの「蜘蛛塚」があります。「土蜘」の後半の場面、退治された蜘蛛を埋めた場所と言われています。再び逃げ出さないよう、巨岩でふたをしたのだそうです。 日本書紀に、昔この辺りに「土蜘蛛族」と呼ばれる一族がいて、大和朝廷に従わず、暴れたので、葛の網で捕まえて殺した、と書いてあるのだそうです。  ここは“高鴨神社”です。大和朝廷より前に栄えた葛城王朝の基礎を築いた「鴨族」の氏神社です。京都の上賀茂神社、下鴨神社も、ここから出たのだそうです。 この日は吉野山に泊まりました。  謡曲「嵐山」ゆかりの“金峯山寺・蔵王堂”です。国宝の建物は、奈良東大寺に次ぐ大建築物です。  蔵王堂からぶらぶらと歩いて“吉水神社”です。謡曲「船弁慶」で大物の浦を出た義経一行は、ここに隠れていました。やがて吉野山も詮議が厳しくなり、謡曲「忠信」や「吉野静」の舞台となって行きます。  吉水神社よりぶらぶらと歩いて、ここは“勝手神社”です。静御前が捕らえられてここで舞ったという話があります。謡曲「二人静」がここが舞台となっております。また、謡曲「吉野天人」もここら辺りが舞台らしいです  これらの堂宇から離れ、谷を挟んだ所の“如意輪寺”です。楠木正行が出陣の時に、堂の扉に書いた辞世の句が残っています。 南北朝の謡曲に「桜井」「楠露」があります。 タクシーで吉野の奥まで出掛けたグループもあります。謡曲「忠信」の“佐藤忠信花矢倉の跡”や“義経隠れ塔”などがあります。 雨模様の旅行でしたが、旅館で謡を謡ったり、仕舞をしたり、楽しい旅行でした。 旅行日 2000年10月 |