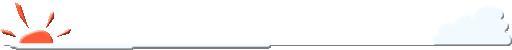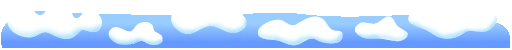
平成18年第2回 能美市6月定例議会だより 2006.6.13〜6.30
| 一般質問 6月21日(水) | |
|
青山利明 質問要旨 1.小・中学生の通学にスクールバスの拡充、コミュニテイバスの活用で安心・安全を確保せよ。 2.不妊治療費70%助成をせよ。 3.妊婦検診を全て無料とせよ。 酒井悌次郎 能美市長 答弁要旨 1.不審者対策としての運行や拡充は考えていない。今後の課題とする。 2.3.同感であるが考えていない。今後、柔軟に前向きに対応したい。 |
| 青山利明 質問詳細 | |
|
能美市議会一般質問 2006.6.21(水)10:00 不妊治療の助成制度の拡充についてお尋ねいたします。 世界の多くの文明成熟国家にとって、少子化は大きな問題となっております。 日本もその渦中に入りました。合計特殊出生率が2.08を下回ると人口減少に転ずるといわれております。現在は1.29にまで落ち込んでおります。2005年、日本の人口は、減少へと転じました。2100年には6414万人と人口が半減すると言われております。 結婚や出産をするか、しないかは個人の意思で自由に選択されるべきです。しかし、労働環境などから意思に反した選択をせざるを得ない方も多いと考えられます。 出産・育児を自己責任の問題ではなく、社会の共同の責任として認識することが大切です。家族、地域、国、社会全体で支援していくためにまずは意識改革からスタートしなければなりません。こどもがのびのび・安全に育つ社会、ゆとりと安心をもって子育ての幸せを実感できる社会の構築が必要です。 長時間労働の是正など生活を犠牲にしない働き方への構造改革。また、若者がニートやフリーターとなり、安定した雇用機会を得にくいことが、未婚、晩婚化を促進しています。若者の安定した就労こそ次世代形成の土台です。 出産・育児を望む人に対しては、仕事との両立の困難さや過重な経済的負担などの阻害要因を取り除き、より積極的に出産・育児の機会を保障することが重要です。 能美市においては子育て先進地として全国に先駆けて様々な子育て支援の施策を講じてまいりました。 今後、更なる充実を望むものであります。 その中で不妊治療の助成制度の拡充については現在、能美市は子宝支援給与金として不妊治療や検査料を回数に制限はなく、一治療につき1/2以内上限15万円となっております。これを治療費、検査量の70%の助成となるようお尋ねいたします。 能美市発足以来、27名が治療を受け、11名の赤ちゃんを授かったと聞いております。私も以前、この治療で授かった赤ちゃんを抱かせていただきました。そのときの感動と手のぬくもり、命の重さは今も忘れることは出来ません。 政府の「少子化社会対策推進専門委員会」も不妊治療の助成拡大を提言しております。5月26日の北國新聞の社説には子どもが欲しくても出来ない夫婦への助成は最も確実な少子対策であり、早急に助成の拡充に取り組む手はずを整えてほしい。と、出ておりました。 石川県は不妊治療の助成制度の拡充に6月補正予算案に1670万円が計上されたと聞いております。一回の治療費に25万円から60万円。治療期間は平均4.67年と聞いております。 治療にいたるまでの心の葛藤、年齢の壁もあります。経済的精神的負担が大きいだけに、安心して治療に専念できるよう酒井市長の英断を望みます。 次に妊婦検診に対する助成の拡充についてお尋ねいたします。 能美市においては、母子手帳の交付を受けて一年以内の妊産及び出産に伴い生じた医療負担保険一部負担金相当額を助成する妊産婦医療費助成制度があります。お母さんと赤ちゃんの状態を常に把握して安心してお産に望めるように妊婦検診についても妊娠中2回産後に1回が無料となっております。妊婦検診は概ね14回受けると聞いております。一回およそ6000円かかると言われ、大きな負担となります。 金沢市は全妊婦に2回分の無料券と1000円の助成券を5回分発行しております。富山県は全妊婦に対して 4回分の無料券を発行、福井県は全妊婦に対して3回分の無料券を発行。ただし、第3子以降には14回分の無料券を発行しております。 能美市においては全妊婦に対して全ての妊婦検診が無料となるよう酒井市長にお尋ねいたします。 次に小・中学生のスクールバスの拡充についてお尋ねいたします。 能美市においては現在、12月から2月の冬季間のみ辰口地区の一部で小学生98名を対象に送迎バスを運行しております。対称地区の通学距離を見ますと2.2キロメートルから4キロメートルとなっております。 対象地区外の通学距離を見ますと、根上地区は下ノ江町2キロ。サンタウン2.2キロ、吉原町2.4キロ、吉原釜屋町2.5キロ、山口町3キロとなっております。 寺井地区においても東任田町2キロ、小杉町2.2キロなどと、なっております。中学生において遠距離通学者は自転車通学をしておりますが、冬季降雪時には家族が送迎をしているのが実態だと聞いております。 能美市民の間では辰口地区の一部のみでなく全市的に小・中学校のバス通学の拡充を望む声があります。 6月補正予算の中には旧3町ごとに走る循環バスに加え、JR寺井駅と北陸先端科学技術大学院大学を東西に結ぶ連携バスを新設する公共交通システムを10月から実験運行するための事業費が計上されております。 能美市公共交通システム構築に関する基本的な考え方についてのなかには高齢者や身障者、子どもなどのいわゆる交通弱者への公共交通の利便性向上とあります。能美市民の間では遠距離通学者や病後時などの生徒を優先に小・中学生の通学にコミュニテイバスの利用を可能となるよう望む声を良く耳にします。 3地区コミュニテイバスの昨年の一台あたりの平均乗車人数を見ますと根上地区6.1人寺井地区11.9人辰口地区8.6人となっております。 新潟県の人口約3万人の加茂市ではより安全で安心できるバス通学を合計24台で全小・中学生の3割約800人が利用していると聞いております。約30年前にスタートした同市のスクールバスは加茂市の説明によると「不審者情報が年15件以上あり、登下校時の安全を考えバス通学を広げた。」とあり、05年に約3000万円を投じて新たに9台を購入して現在の体制となりました。 それまで通学距離2キロ以上を通学距離には関係なく「住宅が途切れる」「交通量が少ない」「通学路に山林や暗くて怖い場所がある」なども対象に加えて、行政区と集落ごとに各学校と教育委員会が協議して決定していると聞いております。停留所にはボランテイアが待機し、子どもたちが家に帰り着くまで見届けている地域もある。と、聞いております。 政府も昨年12月20日の犯罪対策閣僚会議で子どもの登下校時の安全確保へ6項目の緊急対策をまとめ、その一つに「路線バスを活用した通学時の安全確保」を盛り込んでおります。 能美市においてもスクールバスの拡充、コミュニテイバスの活用など柔軟な対応で小・中学生通学時の安心・安全確保を酒井市長にお尋ねいたします。 |
| 市長議案説明 6月13日(火) | |
|
|
 トップページへもどる
トップページへもどる