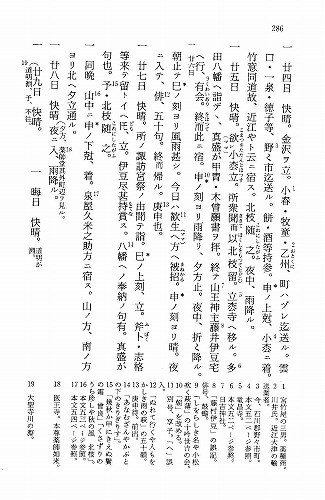mail (ここをクリックしてメールを送って下さいませ)
[1] 地名に込めた芭蕉の想い
[2] 「あかあかと…」の句について
[3] 芭蕉が小松で宿とした「立枩寺」は「龍昌寺」である
[5]「おくの細道」全文
ページ先頭へ
ホームページへ
[1] 地名に込めた芭蕉の想い
ページ先頭へ
地名に込めた芭蕉の想い 〜『奥の細道』掲載の句についての異説〜
内容紹介 歴史ある地名には先人達の秘められた想いが込められている。芭蕉の『奥の細道』にある「しほらしき名や小松吹く萩すゝき」という句について、地名の由来をふまえて、これまでなされてきた解釈とは全く異なった説を開陳したい。
1.「しほらしき名や…」の解釈の疑問
元禄二年陰暦七月、奥州の旅を終えた芭蕉は、北陸道を日本海に沿って南下し、お盆の十五日に加賀の府金沢に着いた。九日間滞在した後、初秋の加賀路を小松に向かった。
紀行文『おくの細道』では次のように記される。
途中吟
あかあかと日はつれなくも秋の風
小松と云ふ所にて
しほらしき名や小松吹く萩すゝき
此所、太田(多田)の神社に詣。真盛(実盛)が甲・錦の切あり。往昔源氏に属 せし時、義朝公より給はらせ給とかや。……(略)。
むざんやな甲の下のきりぎりす
山中の温泉に行くほど、白根が嶽(白山)跡にみなしてあゆむ。左の山際に観音堂あ り。花山の法皇、三十三所の順礼とげさせ給ひて後、……(略)。
石山の石より白し秋の風
この部分、「あかあかと日はつれなくも秋の風」「むざんやな甲の下のきりぎりす」「石山の石より白し秋の風」は『おくの細道』収録の句の中で読者の評判が高い句である。それに対して、「しほらしき名や小松吹く萩すゝき」の句は前後の句に比べて評価が低く、取り上げられることがあまりない。それは次のような理由からであろう。
解説などでは、〈「しほらしき名や」とは、小松という地名の語感と、植物の小松から感じられる「可愛らしさ、可憐さ」を誉めて土地の人たちに寄せた単なる「挨拶句」であり、芭蕉は小松に特別な思い入れは持っていなかった。〉とされる。また、〈「読み下したままでは素直に意味がとれないので稚拙であり、その場の状況を説明しただけのこれといったおもしろみのない駄作である。〉などと酷評されることもある。
筆者はこのような理解に疑問を抱いている。同時に、「しほらし」という形容詞の解釈について、どこか釈然としないものを感じるのである。
紀行文『おくのほそ道』という作品は、死をむかえる年まで数年にわたって自ら推敲に推敲を重ね、心血を注いで完稿されたもので、日本古典文学の白眉である。その文章は収載句とともにすべて作者自信の手よって綿密に構成されており、批判の余地を許さない完璧なものに仕上がっている。
2.形容詞「しほらし」と蕉風俳諧の「しほり」
この句の「しほらしき」は古語辞典にあるままに、「かわいらしい、可憐な」と単純に解してよいのであろうか。花をつけることもない植物の小松は、見ただけで「可愛らしいなあ、可憐だなあ」という詠嘆の念を起こさせるものであろうか。例えば花の小盆栽はともかく松の小盆栽はどうだろう。それに、地名の「小松」という語感は、あえて句に詠込むほどに「かわいく、可憐に」感じられるものなのであろうか。近年、対象についての感動を子供ばかりか大人までもが、これまでの常識では考えられなかったものでも、一様に「かわいい」のみでしか表現できない人が多くなっている。
そもそも小松の地が昔から松や萩すすきの名所であったとか、そのような名所があったとは筆者は聞いたことがないし、記録や文献あるいは言い伝えの類にも全くないのである。たまたま俳席から望める庭に萩やすすきの秋草が植えられていたのでは、というのも安易な考えである。
多くの学習用古語辞典には「かわいらしい、可憐である」の意味の例として、芭蕉のこの「しほらしき…」の句が挙げられている。しかし、別に「しみじみとした趣がある」といった意味もあるのだが…。実は、「しほらし」は、「しをらし」や現代語「しおらしい」との関連において、学会でも未だ十分論議のつくされていない奥深い言葉なのである。
この句は、小松に着いた日の翌日七月二十五日(陰暦)に、小松山王社(本折日吉社)神主藤村伊豆守宅で興行された俳席において作られたものである。「しほらしき名や…」の句は、「あかかと…」の句と同じく、芭蕉本人がも気に入っていたようで、加賀滞在中に地元の人々の求めに応じてものした懐紙が数点残っている。ついでに言うと、芭蕉が小松滞在の二日目から宿としたのは、当時山王社の近くにあった「龍昌寺」(芭蕉に同行した曾良が書き綴った『随行日記』には「立枩寺」とある)という禅寺である。解説書などに「現在小松市寺町にある建聖寺のこと。」と書かれているのは間違いである。龍昌寺は元文年間に小松から金沢へ移転し、現在は能登・輪島市三井の山中にある。
そもそも、この句は俳諧連歌の席でなされた初表八句、初裏十四句、名残表十四句、名残裏八句あわせて四十四句からなる「世吉」という連句の文字通り第一句目の発句である。〈連句の発句は役割の上で、以下に連なる句を象徴したものであって、自然の景趣ばかりでなく人事をも内包されていなければならない。〉とされている。「挨拶句」であるのならば、単なる外交辞令ではなく、〈その土地の風光・歴史など一切に対する親愛の情をも含む〉(角川選書・俳句用語の基礎知識)ものとして当然解釈すべきであろう。ましてや、芭蕉が自らの句に地名を詠み込んだ時は、その土地に対して、なみなみならぬ思い入れを示していると考えてよい。『おくのほそ道』に収録された句で、地名が詠み込まれたものはこれを含めて、松島(曾良の句)、南谷、象潟、佐渡、山中など数例にすぎない。
「わび」とともに芭蕉俳諧の理念のひとつに「しほり」がある。たとえば、芭蕉門下(蕉門)の許六・去来による『俳諧問答』には、〈「しほりと憐なる句は別也。……しほりは句の余勢(余情)に有〉とある。「しほり」は見た目ではなく内に秘められた美であろうか。したがって、「しほらしき」が「しほり」と同一の語基ならば、「しほらしき名や小松…」は、「小松とは可愛らしい名だ」ではなく、「小松とは余情をさそう名だ」と解釈すべきであろう。
芭蕉のこの句がなかったなら、花をつけるわけでない小さな松をして「可愛らしい」ばかりか「可憐な」とまで形容することは多分なかったのであるまいか。この句が作られた背景をよく考慮しないまま、辞書のとおりに安直に解釈しているのではないだろうか。
芭蕉の旅に金沢から小松そして山中温泉まで同行した加賀の北枝による『山中問答』に次のような条がみえる。
〈句文に風雅と言事を忘るべからず。さび しほり 細み しほらしきといふは風雅なり。この心がけなければ、或は平話の句はただ事となり、或は無骨、或は野鄙に心賎しく又、道理に落ちて、俳諧連歌の本意を失う事、道において甚、大切の事とならん。〉
この文の中に、「しほらしき」という形容詞の連体形が、「さび・しほり・細み」という蕉風俳諧の理念を表す名詞の後にあえて付け加えられていることに注目したい。この『山中問答』がなされたのは、「しほらしき名や…」の発句が披露されたわずか数日後である。そう考えると、もしかしたらその際に、蕉風の理念「しほり」についての教示が、この句を例にしてあったのではなかろうか。
3.地名を読み込んだ理由
それにしても芭蕉はどうして「小松と云ふ所にて」と短い詞書きを添えた上で、地名を読み込んだ句を挟んだのか。それについては、今まで詮索した人はほとんど無かったようであるし地元においても同じである。筆者はこれは歓待してくれた土地の人々への単なる挨拶・外交辞令でないと直感していた。芭蕉はこの地名にかなり拘泥していたのである。実は「この地名は平家の小松家に関係する」という事が、二百年数十年もの間、地元でもすっかり忘れられていた。
江戸時代、少しでも教養のある人は、「小松」と聞くと、植物の「松」よりも先に、小松殿(重盛)や小松三位(維盛)そして新小松三位(資盛)など平家の小松家の人々を頭に想い浮かべたはずである。芭蕉は、北国行脚の途上、加賀国小松に着いた時、その地名に何かを感じ取り、土地の人々と語らい謂われを問うてみて、深い余情を感じたに違いない。
平安時代末期、加賀国の国府にほど近いこの地(能美郡)に、平重盛(小松殿、小松内大臣)の所領(つまり荘園)があったという。もちろん源平合戦の末に、無数にあった全国の平家所領地はすべて没官領として取り上げられたから当然記録らしいものはない。しかし、重盛が全国に建立させたと伝えられる祈願寺ないし重盛公ゆかりの小松寺(今日もなお多くが各地に存在している)の一つが、かつてここに存在していたのである。その寺院は長野善光寺のように一宗派に偏らない独立寺院(一本寺)で、小松庄という寺社荘園を領した名刹であったと想像できる。
この地において、少なくとも江戸時代中頃から現在まで、小松寺の存在(地名「小松」の由来なのであるが)はほとんど語られることはなかった。寺伝以外にいわゆる文献史学を満足させる詳しい史料が棄却されて残っていないからでもある。
江戸時代前半期に、当時の一流版元から数度にわたって刊行された明智光秀の一代記『明智軍記』には、地名ないし城名として「小松寺」と明記されている。その記述から、江戸時代以前において、小松は、地名も城名もともに「小松寺」と呼称されていたことが歴然とする。歴史書のうちでも特に軍記物・戦記物では、必須の条件として、そこに記載されている地名や寺院などの建造物の名には実在のものとは異なった偽りのものや、架空のもの、捏造したものが書かれることはないからである。また寺号が地名になることは多いが、平安時代以降では、仏教寺院は所在地の通称をそのまま寺号にすることはほとんどないから、群雄割拠の戦国時代までは、むしろ「小松寺」のほうが正式の呼称であったと考えられる。小松寺とその寺領としての小松庄が存在し、それから「小松」の地名が派生したのである。
戦国時代末期から江戸時代を通じてこの地を領した村上氏、丹羽氏そして前田氏の各領主の都合で、他の一向一揆の遺構と同様に、小松寺の名称と存在そのものが正式の歴史記録から消されたのである。都合の悪い歴史は後代の者によって抹消されることが多い。
芭蕉が小松、山中の次に訪れた大聖寺も、小松のように寺号が城下町の名称になったのであるが、大聖寺は結果的に小松のように地名から寺という字が外れることはなかった。大聖寺城は一国一城制で廃された。芭蕉が訪れる直前の元禄元年に、〈「向後は大正持と書くように〉という通達があえて出されていたが、いつの間にか、お上での記載以外は元のの大聖寺に戻ってしまった。芭蕉に同行した曾良が書き綴った『曾良随行日記』の七月十二日越後糸魚川の条で「大聖寺」とあり、八月五日の山中の条では「大正侍」と記されているのは、この時点での事情をよく反映しており面白い。ちなみに、『おくのほそ道』本文では「大聖持」と書かれている。
一向一揆の城砦となっていた「小松寺」の存在は、江戸時代以降に小松の地を領した各領主家のもとでは憚りごとであったため、正式な歴史として記録されずに、長い間に巷間の記憶から遠ざかり失われていったのであろう。しかし、「小松城は小松殿の小松寺の跡地なり」「小松は小松寺の寺社庄園であった」という事実は、少なくとも江戸時代前半期の地元の人々には常識だったようである。この地を訪れた芭蕉もこのこと(「小松寺→小松」や「大聖寺→大正持」そして「小松殿の小松」であること)をもちろん知っていたに違いないのだが、『おくのほそ道』では憚ってことさら触れることはせず、「小松と云ふ所にて」と短い詞書きをあえて付した上で「しほらしき名や…」の句を載せたのであろう。
旅寝をして現地を訪れた芭蕉が自ら推敲を重ねた結果なのに、後世になってその発句まで「駄作」と評されるのはまことに心外に違いない。『野ざらし紀行絵巻跋』に次のような芭蕉の句がある。
たびねして我句をしれや秋の風
芭蕉の後、江戸中期から現代まで「小松寺→小松」というような歴史的事実が当地の人々の記憶からほぼ完全に失われてしまっていたので仕方がないが、小松の歴史風土を考慮せずに、浅く単純に考えてしまえば、この一見客観的な情景描写風(写生風)の「しほらしき…」の句が削除されても、直前に「あかあかと日はつれなくも秋の風」という秋の季語の句が置かれているので、紀行文としても文脈上はもちろん大差ない。
周知のように、『おくの細道』に収録の句は、すべてが旅の途上で詠まれたものではない。旅の後や『おくの細道』執筆中に作句されたものが多くある。にもかかわらず、後世に酷評までされるにいたったこの句が、あえて載せられているという理由を深く考察するべきであったのではないだろうか。
4.平家小松家と義仲、実盛への芭蕉の想い
それでは芭蕉は小松において、どんな風に余情を感じていたのであろうか。また何を連想したのだろう。
芭蕉は小松山王会での句会を前に多太八幡神社に詣でて、斎藤別当実盛の兜と木曾義仲の願状を見ている。『おくの細道』の記述では「しほらしき…」の句が先にたっているが、その句を詠んだ俳諧の席は多太神社に参詣した後、その日の夕刻からであった。
芭蕉(本名、松尾忠右衛門宗房)は桓武平氏の流れ平宗清(弥平兵衛宗清)の末裔であった。平宗清を祖とする平家一門の家系である。宗清は小松殿平重盛とともに頼朝の命の恩人である。宗清と池禅尼は、平治の乱後に捕えた頼朝の助命を小松殿を介して清盛に嘆願した。まことに数奇な生涯をたどった人物であるが、命を救ったことに対する頼朝からの報恩を甘受することなく平家の滅亡に殉じている。
一方、「むざんやな甲の下のきりぎりす」に詠われた斎藤実盛も木曽義仲の命の恩人であった。その実盛も源氏の義仲軍に対峙し、加賀篠原の戦いで堂々として平家に殉じていった。両人とも平家において一際輝いた英傑であった。多田神社で実盛の兜と義仲の願状を目の当たりにして、平家の忠臣平宗清の後裔たる芭蕉の感慨がどれほど大きなものであったかは容易に察しがつく。
芭蕉が実盛の兜に対面した後の俳諧連歌の席上で、発句に地名をあえて詠み込んだのは、当時すでに城下町としての地名になっていたこの小松という名に、当然ながら平家の小松家を想い起こしたのは当然であろう。この地は小松殿の小松寺をはじめ、涌泉寺・加賀国国府・梯川・安宅・篠原・仏御前の里など『平家物語』にゆかりの多い土地である。
5.連句「しほらしき」の巻について
初表(八句)
しほらしき名や小松ふく萩芒 翁
露を見しりて影うつす月 鼓蟾
躍のおとさびしき秋の数ならん 北枝
葭のあみ戸をとはぬゆふぐれ 斤卜
しら雪やあしだながらもまだ深き 塵生
あらしに乗りし烏一むれ 志格
浪あらき磯にあげたる矢を拾ひ 夕市
雨に洲崎の嵒をうしなふ 致益
(初裏十四句と名残表十四句名残裏八句は略す)
平家物語の悲劇の人、平維盛(小松三位中将)は平清盛の孫であり平重盛の長男である。維盛は木曾義仲討伐の平家軍十万の総大将として北陸道に出陣した。しかし倶利伽罹の戦いから敗退を続け、都落ちして熊野灘に身を投じている。
この俳諧連歌の席において、夕市という人が表八句の七句目に付けた平句「浪あらき…」はまさに維盛の悲哀を詠んでいるのではなかろうか。もちろん『平家物語』ばかりでなく、この地を舞台にした謡曲「実盛」「仏原」「安宅」なども会席者の念頭にあったであろう。また、彼らは『源氏物語』の世界にも遊んでいる。
鼓蟾(藤村伊豆守)が芭蕉翁の発句に添えた脇句(第二句目)「露を見しりて影うつす月」は、『源氏物語』の有名な「御法の巻(萩の上露)」を連想させるものでないだろうか。この巻で、風の吹く秋の夕暮、病に伏す紫の上を光源氏と明石の中宮が見舞いに訪れる。
おくと見るほどぞはかなきともすれば風にみだるる萩のうは露
儚い命を萩の上露にたとえて互いに詠み交わすうちに、紫の上はこときれる。ここは物語の圧巻で、最も悲しくも美しい場面である。
それは『源氏物語絵巻・御法』に実に巧みに描かれている。紫の上の邸の前栽には、強い秋風に露を置いた萩や薄などの秋草が大きくなびいて、その風は簾を押して室内に吹き入っている。紫の上と光源氏、明石の中宮の三人は、ともに涙を袖で拭う。当然その袖は「しほれて」いる。よく見ると、銀泥を掃いた暗闇の部分は、月影(月光)を映じた無数の露の表現である。日本の仏教では、露の一粒一粒全てに真如の月が宿されているとするが、「影うつす月」は何と幻想的で美しい情景であろう。
しほらしき名や小松ふく萩すゝき
露を見しりて影うつす月
鼓蟾が添えた脇句は、芭蕉の発句の「萩すゝき」を見事についでいるといえないだろうか。
『山中問答』に次の条もみられる。
〈脇の句は、発句と一体のもの也。別に趣向奇語を求むべからず。只、発句の余情をいひあらはして、発句の光をかかぐる也。〉
「しほらしき」の上五文字で起こすこの発句は、単独でなく鼓蟾の脇の句とあわせて味わいたいものである。思うに、この句は「蕉風俳諧」の美の理念である「しほり」というものを、その時に会した小松の人だけではなく「蕉風俳諧」に志す者に示した枝折(手引き)だったのではなかろうか。
ページ先頭へ
ホームページへ
[2] 「あかあかと…」の句について
ページ先頭へ
「あかあかと…」の句について 平成十一年(1999年) 小松文芸賞(小松文芸47号)
一、さまざまな解釈
あかあかと日はつれなくも秋の風
紀行文『おくの細道』の構成にあたって、芭蕉翁はこの句を「途中吟」として、金沢から小松に至る聞に入れている。日足も目に見えて短くなった初秋の夕方を想像すれば、小松に着く直前ということになる。ところが、この句は残暑きびしい折りに、越後路から越中路を、加賀の府金沢に向けて歩んでいた時に発想されたのであろうと考えられている。盆の十五日に金沢に到着してまもなくの句会の席で披露されているからだ。『おくの細道』本文の中で、富山湾内の奈呉の浦から倶利伽羅峠、あるいは峠から金沢への場面に挿入せずに、どうしてわざと小松の前に配したのであろうか。
最近になって発見された加筆訂正の多い直筆原本でその部分を見てみると、芭蕉翁は構成の早い段階でここに置くことに決めていたように筆者には思える。このような疑問や句の本意について考察してみたい。
詩歌には当然のことかもしれないが、この句の解釈についても人によって違いがみられる。普通は「もう秋が立っているというに、夕日はそれも知らぬげに兼行くわたしの上に赤々と照りつけ、残暑はなおきびしいが、しかし、さすがに目に見えぬ風のおとずれには、やはり秋の風だなぁと感ぜせしめるものがある。(『おくの細道』頴原退蔵・尾形仂訳註 角川文庫)」というふうに解され、ほぼ定説となっている。
上旬の「あかあかと日は……」の語句について異説があり、江戸時代には「赤い」よりも「明るい」という意味で使われることが多かったので、夕日ではなく日中の太陽であるとか、またむしろ朝日だとする解釈もある。発想時点でのようすを想像すれば、そう考えても無理はない。また古語の「つれなし」は「関係がない。そっけない。冷淡だ。なんの変化もない」と意味に暗があるが、現代語ではほとんど「無情だ」「薄情だ」の意味のみに使うのでそのように意訳する例もある。
前掲書にも紹介されているように、芭蕉翁自身はこの句が気にいっていたようで、たびたび求めに応じて書いた自画讃には、萩すすきの向こうに沈みゆく赤い夕日を配したものもある。また其蹟のなかに前書に「めにはさやかに、といひけむ秋立けしき、薄・かるかやの葉末にうごきて、聊か昨日に替る空のながめ哀れなりければ」とあり、また「……さすがに目に見えぬ風のおとづれもいとゞ悲しげなるに、残暑猶やまさりければ」というのもあることから、古今和歌集(秋歌上 藤原敏行)
秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる
という和歌をふまえたものであろうとされている。そこで解釈として、当然ながら「残暑」や「秋の風」 におおきく力点が置かれる。しかし筆者はむしろ上五句のはうにもっと意を置いたはうが、翁の心により近付くことができると考える。
解釈の違いは、たった十七文字に込めなければならないゆえの限界とか、俳句を作る人おのおのの思想や人生観、またその流派の違いなどもその原因にあげられて、「かえって自由に解釈できるところにおもしろさ、俳句というもののおくゆかしさがあるのだ」と説明される。これには返す言葉がない。しかし「芭蕉といえども『奥の細道』には、冗長な、あいまいな、上出来でない句もあるのは当然」というような解釈があるのには首をかしげざるをえない。
俳譜を革新し、近代俳句の創始者となった正岡子規はその著『芭蕉雑談』(明治二十六年)のなかで、この句を
あかあかと日の入る山の秋の風
と改作を試み、「兎に角にこの句を称して芭蕉集中二十三章の秀逸となす事、返す返すも不埒なる言い分なりけらし」と酷評している。
およそ『万葉集』や勅撰和歌集などの中に秀歌やそうでないものなどの上下があるはずはなく、当時の一流の歌人が膨大な数のなかから撰んだもので、歌集中に何千首あろうとすべて秀歌なのである。
それ同様に『おくの細道』に載せられた発句は、一つの句の推敲に数年もかけることがあった芭蕉翁が、決定稿ができる直前まで本文とともに自ら推敲に推敲をかさねたもので、彼は五年近い歳月をかけ心血を注いで、この紀行文を完結している。本人は刊行(上梓)するつもりのなかったいわば白鳥の歌である。歴史が証明するとおり、まさに『源氏物語』などと並んで日本の古典文学を代表する作品となった。
子規の批判にもかかわらず、江戸時代から今日まで多くの評者がこの句を高く評価してきたことは間違いない。思うに、これを理解するためには近代俳句の立場ではなく、俳諧発句という古典文学とくに蕉風俳諧という視点に立ってみることが、必要なのではないだろうか。
俳句は明治の頃までは、一句でも発句とよばれていた。発句は芭蕉翁によって俳諧連句からはなれて単句として高度な芸術になった。それは文字通り連句の第一句日の長句(五七五)の性格をもともと有しているゆえに、季語はもちろん余情余韻が富かなものでなければならない。「さび」や「しはり」その他の理念が重視されるのはそのためである。
言うまでもないことだが、俳諧は連想の芸術であり、作句者は和漢の詩歌の知識はもとより、物語、謡曲、歴史、宗教(神祇・釈教)はもちろんその時点での興味・心情そして地方にあってはその土地の風土・歴史など森羅万象を深く考慮にいれて詠じている。受け手はそれを説明されることなく直感で解することを求められる。
『おくの細道』に入句された発句は、句だけを取り出して字面だけで評価してもあまり意味をなさないばかりでなく、誤解されることになる。あくまでも本文の内容、作者の心情にそって味わうことがどうしても必要になる。芭蕉翁はそのことを
旅寝して我句を知れや秋の風
という句(『野ざらし紀行絵巻』奥書)にしてうったえている。
二、俳諧の解釈の難しさと「心ある人」
俳諧の解釈は、それが日本の近世のものであるにもかかわらず、文学作品のなかでもっとも難しいものの一つで、とりわけ歌仙などの連句を解釈する困難さは、和歌や連歌の比ではないといわれる。当時の俳諧連歌を嗜んだ一般庶民(庶人)の教養は、日本の古典文学はもとより漢籍、仏典にも幅広く通じており、その造詣の探さは、われわれ現代人の想像をはるかにこえている。また江戸時代二百数十年間の庶民の考え方や生活様式に関する現代人の知識は、明治期と昭知期後半の短期間に二度の価値観や思想の根本的な転換があったにもかかわらず、わずか数世代まえの近世のことで文献も比較的多く残っているのでなんとなく理解しているつもりでいるが、実はほとんど解っていないと言っていいほど浅いのである。
近代とくに戦後は一貫して、歴史学者をはじめ多くの人は次のような固定した観念で江戸時代をみなしてきた。すなわち、この時代は封建社会のわくぐみとその支配原理のもとで庶民は半ば奴隷化しており、宗教もその支配体制に迎合していた。そのような封建制に対する抑圧された不満のはけ口とか精神的な逃避のひとつの手段として人々は例えば俳諧などを嗜んでいた。
このような理解は、封建制度という概念についてもそうであるが、大変な誤解であるということが近年になって次第に明らかになり見なおされはじめた。そのような予断と偏見のもとに当時の文化を理解しようとしても、誤解や曲解が生じるのは当然のことなのかもしれない。ましてや文芸としての俳諧をはじめとする諸芸術(風雅)は、なにも一部の特権階級のみのものではなく、われわれ現代人の勝手な想像に反して、おおいに闊達であった当時の一般の人々がその幅広い教養や深い宗教心をもとに、人生をより充実したものにしたいという向上心の求むるところから発達し普及してきたものであった。解釈が分かれる原因の一つはそのへんにあるのかもしれない。
子規の近代俳句の急進性に疑問を抱いた高浜虚子は、季題や花鳥諷詠の重要性を主張し、芭蕉俳諧への復帰をめざした。しかし「花鳥風月は月並みであり垢のついた古くさいもの」とする人々の思い込みと、近代化という「西欧文明化」への大きな波には逆らえなかったのであろうか、不備に終わっているようだ。さらに第二次大戦後の定見のない民主主義にもとづいた思想、宗教の自由や科学的合理主義は、日本文化の特質である「心」「道」あるいは「型」などという観念を文字通り有名無実なものにしてしまった。
近ごろ、青少年のこれまでと違った異常な行動が目立つようになってきて、にわかに「心の教育」の重要性がさけばれるようになってきた。しかし教育する立場の親はもちろん社会の指導者を自認する人々の多くは、これまで「心」の問題についてあまり深く考えてはこなかった。したがって、考えおよぶことは場当たり的で、言葉だけの「道徳」「やさしい心」「おもいやりの心」あるいは「スポーツマン精神」などしか発想ができなく、その実践として無垢な子供に近頃はやりのボランティア活動をすすめ、老人ホームへの慰問をさせたり、世界の恵まれない子供を援助する活動、スポーツによる子供の国国際交流など、さらには世界平和運動にもと当然のごとく向かわせることになる。
日本では昔から「心ある人」というのは、四時(季節)の細やかな変化を敏感に感じとることのできる人であるとされてきた。そうでない人は身分の上下に関係なく尊敬されなかった。季節の変化を象徴するのが、花鳥風月・雪月花であり、人間界もふくめた森羅万象を意味するのである。つまり風流を解することも生きていくうえでとても大切なことであり、そのための精神修養が和歌の道などをはじめとする風雅の道(芸術)であり宗教であった。風流というと直ちに貴族趣味と判で押したように返ってくるのは、唯物的なものの見方を知らず知らずのうちに身につけてしまった人々の常で、『万葉集』にもみられるように古来から風流については身分や貴賎を問われることなく、その意味でいわば人は平等であった。また森羅万象を讃えるということはとりもなおさず神仏への道、すなわち宗教と密接にかかわってくる。人間の心について深く考えてきたのが宗教にほかならなく、心の教育とはつまるところ宗教や倫理、そしてそれにつながる芸術(芸道)にかかわる問題であり、ボランティア活動や平和運動などはむしろ二次的な問題ではなかろうか。
三、「あかあかと…」の句を味わう
「あかあかと…」の句を、味わい解するには参考にしたい句がいくつかある。
暑き日を海に入れたり最上川
同じ紀行文中では酒田で吟じたことになっている。周知のように、同行した河合曽良の『俳諧書留』などによれば、この旬の初案は
涼しさを海に入たる最上川
として、上五旬は異なっていた。それが「暑き日を」と改められたのは旅の後、『おくの細道』執筆で初稿の段階であるらしい。
「暑き日を……」の句の解釈としては、
「赤い夕日が海に沈もうとしている。暑い一日を、大河の水に浮かべて海に流し入れてしまったのだ。流れ終えた最上川の河口のあたりからは、涼しい夕風が立ちはじめている。(前掲書)」と意訳される。
ここで問題になるのは、「暑き日」が「太陽」をさすのかということになる。ふつうは「涼しさを……」の句によって「暑き日」は直接「太陽」をさすのではなく、この評釈者も述べているように「暑き一日」であるとする。筆者はここでは直接に太陽、しかも入日を重視して、「暑き一日」は間接的なものと考える。
弥生三月に江戸の深川を旅立った芭蕉は、念願の松島をみてから平泉をへて列島を横断し、月山に登山してから最上川を船で下り、日本海の河口にある酒田に到着する。季節は真夏である。月山で宇宙の法(のり)を体感した翁は、酒田ですばらしい入日をみて大きな感動をおぼえたに違いない。鎌倉時代以降、禅とともに日本の芸術に多大な影響をあたえた『新古今和歌集』に、藤原俊成による次の和歌がある。
今ぞこれ入日を見ても思ひ来し弥陀のみ国の夕暮の空
酒田での感動が後になって「涼しさを…」を「暑き日を…」と改作した最大の動機であったのでなかろうか。
日本海側では、入日は山に入るのではなく、西方の海の彼方に没するのである。芭蕉は生れてからこの時まで、紀伊半島をはじめ旅行などで尾張や近畿に、また江戸における住いと、ほとんどが太平洋側で暮らしており、夕日が水平線に没する美しく厳かな光景を直接目のあたりにすることはめったになかったであろう。子規自身もそうであったにちがいない。お釈迦さまは『観無量寿経』のなかで西に沈む太陽を観て瞑想する事を第一番目に説かれた。日想親である。夕日が山に入ってしまう太平洋側では、この日想観を行うに適当な場所がほとんどない。
酒田を後にして、芭蕉翁は北陸道を加賀の府に向けて南下するわけだが、暑いのにあえて海沿いの浜街道を通って行く。しかし天気さえ良ければ毎日でも日想観を行える。金沢に着くころには残暑はきびしいが季節はすでに秋になっていた。到着の翌々日にはさっそく立花北枝の幻意庵で催された秋の納涼句会に出席することになる。ここで金沢の小春は、立句となった「あかあかと日はつれなくも秋の風」に続けて詠んでいる。
入相や盆の過ぎたる鐘の音
この二句をくらべてみると、翁が季題の秋の風よりも残暑よりも、入り日により意をおいていることをくんで、小春が詠んだように思われる。翁自身も旅の途上「……悲しさもまさりて塩竈の浦に入相の鐘をきく」と感動している。この席でそのことが松島や象潟の景勝と合わせて旅のみやげ話になったのかもしれない。
そのちょうど一年後の夏に、芭蕉翁が石山寺にほど近い国分山の幻住庵にこもっている時に、翁が金沢を訪れた際に門下になった金沢の秋之坊という人が訪問した。そこで句をひとつあたえられている。
やがて死ぬけしきは見えず蝉の声
これは芭蕉真蹟の前書きに「無常迅速」とあるように、「無常迅速の句」といわれる。この句と「あかあかと日はつれなくも秋の風」の句をくらべてみると、場面と季題のちがいはあるが、心は同じと筆者は感じるのである。「けしきはみえず」は「つれなくも」とよく似た意味に使っているようだ。そうすると、「あかあかと…」の句もまた「無常迅速の句」とみてもよいのではないだろうか。
秋之坊が幻住庵を訪れたとき、芭蕉翁は一代の名文『幻住庵の記』の草稿にとりかかっていた。同時に紀行文『おくの細道』の構想をもねっていたであろう。この『幻住庵の記』や翁自身の手紙にはこの「無常迅速」という言葉をよく使っている。
『新古今和歌集』羇旅歌に、藤原定家による夕日と秋風の歌(旅の歌とてよめる)がある。
旅人の袖吹きかへす秋風に夕日寂しき山のかけ橋
この歌にも注目してみたい。これは翁が好んだ白楽天の『長恨歌』を典拠としているといわれている。芭蕉翁は古典の中でも『新古今和歌集』をとくによく読みこなしており、西行法師には深く傾倒している。この定家の歌と先にあげた俊成や敏行の歌、そして西行の心をふまえて、無常と静寂を詠じたのがこの発句なのではなかろうか。まさに蕉風俳諧の真骨頂といえよう。
それでは、なぜ小松の前に「あかあかと…」の句を配したのであろうか。次に続く句をならべてみて、筆者なりの考えを添えてみる。
あかあかと日はつれなくも秋の風
(舐園精舎の鐘の声、諸行無常の事あり…の平家物語冒頭を想起させる)
しぼらしき名や小松ふく萩すすき
(小松内大臣平重盛をはじめ小松家の人々、とくに小松三位維盛の哀れさを想起させる)
むざんやな甲の下のきりぎりす
(もちろん斎藤別当実盛を想起させる)
石山の石より白し秋の風
(粟津ヶ原に露と散った木曽義仲を想起させる)
『おくの細道』紀行のあと芭蕉がこもった石山寺近くの幻住庵から、眼下に粟津と義仲寺そして琵琶湖を望める)
思うに、芭蕉翁がその地名を心につよく留めた「小松」を舞台に突如として、『平家物語』の世界が展開するのである。このように作者は『おくの細道』の中で、『源氏物請』、『伊勢物語』、謡曲など数々の古典を題材にして、さまざまな趣向をこらして読むものを楽しませてくれるのである。
四、蕉風俳諧と仏教
芭蕉の俳諧を考察していくうえで、仏教とくに禅をぬきに語ることはできない。もちろん蕉風俳諧に限ったことではなく、明治期までの日本の古典芸術・古典文学全般にわたることである。
室生犀星は自ら俳句をつくり、すぐれた芭蕉論を書いているが、その著『芭蕉襍記』(昭和三年)のなかでこう述べている。
「彼はこの世を諸行無常だと思うてゐない。彼はこの世をさびしいものだといふ風に考え耽っていても、無常だといふことに片づけてゐないのである。この世の中で彼の必要なものは「静さ」であり「しめやかさ」であり、「さびしをり」であった。しかし此の世を詰まらない無常だとか思うてゐない。ままならぬが故にさびしくは観てゐるのである(以下略)」
芭蕉翁は四十歳をこえた頃からすでに、まわりの人々から翁と尊称されていた。仏教とくに禅の道(仏頂和尚について修禅して印可をうけている)にはかなりの域に達していたようである。
「彼はこの世を諸行無常だと思うてゐない」というのには筆者は合点がいかない。考えるに、犀星は仏教の諸行無常の「無常観」と日本の古典文学の「無常感」とを混同していたのではなかろうか。たしかに、日本の文学には「非情な」とか、「世をはかなんで」あるいは「世を捨てる」という厭世的な感傷的な雰囲気はつねにある。それは日本文学特有の哀愁感であり「無常感」であろう。しかし、仏教の「諸行は無常なり」の「無常観」は宇宙の大原理をいうのであって、この世が厭わしいところなのか、生きるに値するところなのか、どうとらえるかは個人の問題であるけれども、仏教ではもちろん後者のはうを勧めその方法を説いている。このことは仏教を信心なさっておられる方ならば言うまでもないことであろう。
『源氏物話』にしても『平家物語』にしても、表面上は哀愁ただよう「無常感」を感じとれるが、よく読んでみるとさまざまな登場人物の生きざまをとおして生への執着、つまり今生を充実して生きることをそれ以上にうったえているように思えてならない。
犀星は「この世の中で彼の必要なものは、『静さ』であり『しめやかさ』であり『さびしをり』であった」と述べているが、筆者もこのとおりだとは思う。
『涅槃経』のお釈迦さまの言葉
諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為楽
(諸行は無常なり、是れは生滅の法、生滅が滅し已って後、寂滅をもって楽と為す)(この世のあらゆるものは常に移りかわっていく、生じたものは必ず滅する、これは宇宙の法則である、それを悟って無我になれば、静寂への喜びを得ることができる)意訳は筆者が先学の方の解説を参考に、自分なりにつぎあわせてみた。
仏教は「空」すなわち「無常」を教義の始点としており、それにそった日本の古典芸術・古典文学は自然(花鳥風月)と一体になり(同化し)、静寂の境地に至ることを目指してきた。それを発句として十七文字に集約させ、俳諧をいわば芸の道に昇華させえたことが、芭蕉翁のすぐれた才能であり偉大さであったといえる。その作品が三百年以上たった今もまったく色あせることなく、日本人の心をとらえてはなさないのは、まさしく真理をついているからにほかならないゆえであろう。翁は無常迅速を常に心にしていた。これは宗教者ばかりでなく江戸期までの日本人にはごく自然のことであったろう。
ちなみに俳号「芭蕉」は、ふつうはその大きな葉をもっているがゆえに「風に破れやすく、脆くてじつにはかないもの」ととらえてその面だけを解説されるが、仏典ではむしろ「夢・幻・泡・影」、「露・雷」あるいは、「空蝉」と同じく「空」であり「無常」であることの例えにつかわれる。この植物には堅い芯がないからである。(是の身は芭蕉の如く、中に竪さ有ることなし『推摩経』)
禅を修め悟道を歩んだ薫翁の生き方、句作の姿勢は「空」になりきった「無我・無心」の境地であり、その句の多くはこの無常観をもとに静寂にいたる(翁の言葉をかりると「寂滅の心を悟り侍る」)その悦びを詠んだものと思う。とくに夕暮れの静けさを好んだようである。そのとおり、『おくの細道』の終局において敦賀湾内の小さな漁村、種の浜では次のように記している。
浜はわづかなる海士の小家にて、侘しき法華寺あり。ここに茶を飲み、酒を暖めて、夕暮れの寂しさ、感に堪へたり。
寂しさや須磨に勝ちたる浜の秋
ここは『おくの細道』のなかで筆者のもっとも好きな場面の一つである。この土地は地味なところで訪れる人はあまりないようだが、当時のことがよく偲ばれる。山水画の「漁村夕照」の景を彷彿とさせ、浜辺にいるとその閑寂さに絶句した翁の心境がわかるような気がしてくる。(了)
評
後藤氏の作品については、後半の若干の部分において小生個人としてはある種の異論を持つ。たとえば「花鳥風月」を愛する風流人は、永六輔が風刺するように自然保護運動には意外にも無関心といわれる。とはいえ花鳥風月の美的人生を一方的に否定するつもりはない、個人の自由なのだから。次に、「定見のない民主主義」に関しては、ご存じのように、アメリカ独立戦争からフランス革命に至る民主主義をめぐる血と汗の闘いとその後の成熟を通じて、今日の日本における農地解放、男女共学、労働組合、失業保険、年金など社会の基礎制度がもたらされた。もちろん西欧文化への無批判的礼讃には賛同しない。ヘーゲルの弁証法を引くのは些か書生論っぽいが、執筆者の論点、その反論など各自の意見は総合へと止揚される過程のテーゼ、アンチテーゼとして役立つであろう。
とにかく、後藤氏の作品は、全体として論旨は首尾一貫して、明白であり、好論文として評価したい。
ページ先頭へ
[3] 芭蕉が小松で宿とした「立枩寺」は「龍昌寺」
ページ先頭へ
芭蕉が小松滞在の二日目から宿としたのは、当時山王社の近くにあった「龍昌寺」という禅寺である。(芭蕉に同行した曾良が書き綴った『随行日記』には「立枩寺」とある)
『おくの細道』の解説書などに「建聖寺の誤記」「現在小松市寺町にある建聖寺」などと書かれているのは間違いである。『随行日記』に「立枩寺」とあるのは曾良の誤記なのではなく昔の人の書いたものによくある宛字である。
「立枩寺(立松寺)」(竜昌寺)は元文年間に小松から金沢へ移転し、今は能登・輪島市三井の山中にある。
現在の龍昌寺の様子は、平成15年(2003)4月30日から5回にわたって北國新聞に掲載された。

 平成9年(1997年)10月16日付の北國新聞・文化欄に〈芭蕉が泊まった小松の寺「立枩寺」は龍昌寺か〉という見出しで掲載されている。
平成9年(1997年)10月16日付の北國新聞・文化欄に〈芭蕉が泊まった小松の寺「立枩寺」は龍昌寺か〉という見出しで掲載されている。
平成18年7月刊の『奥の細道行脚(曽良日記を読む)』(櫻井武次郎)では、左のように記述されている。ただし、《「立松寺」が龍昌寺の誤記であることを・・・》と書かれているので、誤解されやすい。「立松寺」は誤記ではなく宛字である。
「立枩寺は建聖寺」とされるようになったのは、岩波文庫の『おくの細道』や角川文庫の新訂『おくの細道』に《「建聖寺」の誤記か。》と注書されていることに大きな原因があるのであろう。「誤記か」の「か」を無視ないしは読み違えて、「誤記」と断定してしまい、それが訂正されることなく、次々とそのまま孫引きされてしまったのである。
今の小松市内には、龍昌寺が存在しないこと(昭和40年のはじめまで「龍昌庵」という曹洞宗の尼寺があった)と、建聖寺には立花北枝の作とされる芭蕉木像(小松市文化財指定)と江戸期建立の「しほらしき・・」の句碑があることなどから、地元小松の研究者もそのまま鵜呑みにしてしまい、『新修 小松市史 資料編7 文芸』の記載などに見られるように、いまだに「芭蕉は建聖寺に宿泊した」と思いこんで不思議に思わない人がほとんどである。建聖寺を「たてしょうじ」と強引に重箱読み(寺号は重箱読みしない)してまでも、「立枩寺」=「建聖寺」とする論考もあるほどである。
北國新聞・文化欄の〈芭蕉が泊まった小松の寺「立枩寺」は龍昌寺か〉は平成9年(1997年)地元郷土史の会が刊行した『加南地方史研究 第44号』(平成16年)やその他に寄稿した拙稿を要約したものである。「立枩寺」が「龍昌寺」であることは、大河良一氏がすでにその著書『加能俳諧史』において指摘されていたのを、地元研究者としてあらためて検証したまでである。
角川文庫・昭和42年・新訂『おくの細道』(右下)では《「建聖寺」の誤記か。》とされていたのが、角川文庫・平成15年・新版『おくの細道』(左下)では《竜昌寺。》に訂正されている。(その下に新旧を拡大してならべてある)
しかしながら、平成18年5月刊の『新修 小松市史 資料編7 文芸』(小松市史編集委員会)〈第1章古典文芸にみる小松 第6節紀行文 10おくの細道(抄)〉には「「立松寺」の文字に〔建聖寺カ〕と添えてある。また、地元郷土史の会「加南地方史研究会」の会誌『加南地方史研究 第51号』(平成16年)「曽良の生涯(その4)」にも
「立枩寺(建聖寺」)」「立松寺は誤り」「建聖寺泊」と記された研究論文が掲載されている。地元の一研究者としてひじょうに残念なことである。
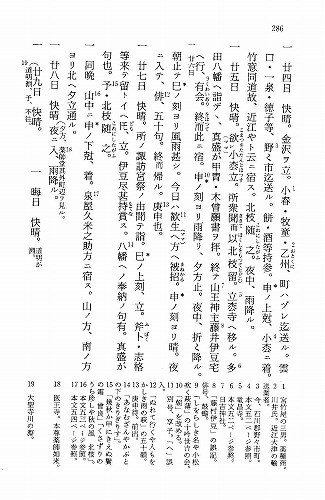

角川文庫・平成15年・新版『おくの細道』(左上・左下) 昭和42年・新訂『おくの細道』(右上・右下)

(左下)『新修小松市史 資料編7文芸』 (右下)『加南地方史研究 第51号』(平成16年)






ページ先頭へ
ホームページへ
[5] >「おくの細道」全文
ページ先頭へ
「おくの細道」(全文)
月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる物は日々旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか片雲の風にさそはれて、漂白の思ひやまず、海濱にさすらへ、去年の秋江上の破屋に蜘の古巣をはらひてやゝ年も暮、春立る霞の空に白川の関こえんと、そゞろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて、取もの手につかず。もゝ引の破をつゞり、笠の緒付かえて、三里に灸すゆるより、松嶋の月先心にかゝりて、住る方は人に譲り、杉風が別墅に移るに、
草の戸も住替る代ぞひなの家
面八句を庵の柱に懸置。
弥生も末の七日、明ぼのゝ空朧々として、月は在明にて光おさまれる物から不二の峯幽にみえて、上野谷中の花の梢又いつかはと心ぼそし。むつまじきかぎりは宵よりつどひて舟に乗て送る。千じゆと云所にて船をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて幻のちまたに離別の泪をそゝく。
行春や鳥啼魚の目は泪
是を矢立の初として、行道なをすゝまず。人々は途中に立ならびて、後かげのみゆる迄はと見送なるべし。
ことし元禄二とせにや、奥羽長途の行脚、只かりそめに思ひたちて呉天に白髪の恨を重ぬといへ共耳にふれていまだめに見ぬさかひ若生て帰らばと定なき頼の末をかけ、其日漸早加と云宿にたどり着にけり。痩骨の肩にかゝれる物先くるしむ。只身すがらにと出立侍を、帋子一衣は夜の防ぎ、ゆかた雨具墨筆のたぐひ、あるはさりがたき餞などしたるはさすがに打捨がたくて、路次の煩となれるこそわりなけれ。
室の八嶋に詣す。同行曾良が曰、「此神は木の花さくや姫の神と申て富士一躰也。無戸室に入て焼給ふちかひのみ中に、火々出見のみこと生れ給ひしより室の八嶋と申。又煙を讀習し侍もこの謂也」。将このしろといふ魚を禁ず。縁記の旨世に傳ふ事も侍し。
卅日、日光山の梺に泊る。あるじの云けるやう、「我名を佛五左衛門と云。萬正直を旨とする故に人かくは申侍まゝ、一夜の草の枕も打解て休み給へ」と云。いかなる仏の濁世塵土に示現して、かゝる桑門の乞食順礼ごときの人をたすけ給ふにやとあるじのなす事に心をとゞめてみるに、唯無智無分別にして正直偏固の者也。剛毅木訥の仁に近きたぐひ気禀の清質尤尊ぶべし。
卯月朔日、御山に詣拝す。往昔、此御山を「二荒山」と書しを空海大師開基の時「日光」と改給ふ。千歳未来をさとり給ふにや。今此御光一天にかゞやきて恩沢八荒にあふれ、四民安堵の栖穏なり。猶憚多くて筆をさし置ぬ。
あらたうと青葉若葉の日の光
黒髪山は霞かゝりて、雪いまだ白し。
剃捨て黒髪山に衣更 曾良
曾良は河合氏にして、惣五郎と云へり芭蕉の下葉に軒をならべて予が薪水の労をたすく。このたび松しま象潟の眺共にせん事を悦び、且は羈旅の難をいたはらんと旅立暁髪を剃て墨染にさまをかえ惣五を改て宗悟とす。仍て黒髪山の句有。「衣更」の二字力ありてきこゆ。
廿餘丁山を登つて瀧有。岩洞の頂より飛流して百尺千岩の碧潭に落たり。岩窟に身をひそめて入て滝の裏よりみれば、うらみの瀧と申傳え侍る也。
暫時は瀧に篭るや夏の初
那須の黒はねと云所に知人あれば是より野越にかゝりて直道をゆかんとす。遥に一村を見かけて行に、雨降日暮る。農夫の家に一夜をかりて、明れば又野中を行。そこに野飼の馬あり。草刈おのこになげきよれば、野夫といへどもさすがに情しらぬには非ず「いかゝすべきや、されども此野は縦横 にわかれてうゐうゐ敷旅人の道ふみたがえん、あやしう侍れば、此馬 のとゞまる所にて馬を返し給へ」とかし侍ぬ。ちいさき者ふたり馬の跡したひてはしる。独は小姫にて名を「かさね」と云。聞なれぬ名のやさしかりければ、
かさねとは八重撫子の名成べし 曾良
頓て人里に至れば、あたひを鞍つぼに結付て馬を返しぬ。黒羽の館代浄坊寺何がしの方に音信る。思ひがけぬあるじの悦び、日夜語つゞけて、其弟桃翠など云が朝夕勤とぶらひ、自の家にも伴ひて、親属の方にもまねかれ日をふるまゝに、ひとひ郊外に逍遥して、犬追物の跡を一見し、那須の篠原わけて玉藻の前の古墳をとふ。それより八幡宮に詣。与一扇の的を射し時、「別しては我国氏神正八まん」とちかひしも此神社にて侍と聞ば、感應殊しきりに覚えらる。暮れば、桃翠宅に帰る。
修験光明寺と云有。そこにまねかれて行者堂を拝す。
夏山に足駄を拝む首途哉
当国雲岸寺のおくに佛頂和尚山居跡あり。
竪横の五尺にたらぬ草の庵
むすぶもくやし雨なかりせば
と松の炭して岩に書付侍りと、いつぞや聞え給ふ。其跡みんと雲岸寺に杖を曳ば、人々すゝんで共にいざなひ、若き人おほく道のほど打さはぎて、おぼえず彼梺に到る。山はおくあるけしきにて谷道遥に、松杉黒く苔したゞりて、卯月の天今猶寒し。十景尽る所、橋をわたつて山門に入。
さてかの跡はいづくのほどにやと後の山によぢのぼれば、石上の小庵岩窟にむすびかけたり。妙禅師の死関、法雲法師の石室をみるがごとし。
木啄も庵はやぶらず夏木立
と、とりあへぬ一句を柱に残侍し。
是より殺生石に行。館代より馬にて送らる。此口付のおのこ、短冊得させよと乞。やさしき事を望侍るものかなと、
野を横に馬牽むけよほとゝぎす
殺生石は温泉の出る山陰にあり。石の毒気いまだほろびず。蜂蝶のたぐひ真砂の色の見えぬほどかさなり死す。
又、清水ながるゝの柳は蘆野の里にありて田の畔に残る。此所の郡守戸部某の此柳みせばやなど、折々にの給ひ聞え給ふを、いづくのほどにやと思ひしを、今日此柳のかげにこそ立より侍つれ。
田一枚植て立去る柳かな
心許なき日かず重るまゝに、白川の関にかゝりて旅心定りぬ。いかで都へと便求しも断也。中にも此関は三関の一にして、風騒の人心をとゞむ。秋風を耳に残し、紅葉を俤にして、青葉の梢猶あはれ也。卯の花の白妙に茨の花の咲そひて、雪にもこゆる心地ぞする。古人冠を正し、衣装を改し事など、清輔の筆にもとゞめ置れしとぞ。
卯の花をかざしに関の晴着かな 曾良
とかくして越行まゝにあぶくま川を渡る。左に会津根高く、右に岩城相馬三春の庄、常陸下野の地をさかひて山つらなる。かげ沼と云所を行に、今日は空曇て物影うつらず。すが川の駅に等窮といふものを尋て、四五日とゞめらる。先白河の関いかにこえつるやと問。長途のくるしみ身心つかれ、且は風景に魂うばゝれ、懐旧に腸を 断てはかばかしう思ひめぐらさず。
風流の初やおくの田植うた
無下にこえんもさすがにと語れば、脇第三とつゞけて、三巻となしぬ。
此宿の傍に、大なる栗の木陰をたのみて、世をいとふ僧有。橡ひろふ太山もかくやと間に覚られてものに書付侍る。其詞、
栗といふ文字は西の木と書て西方浄土に便ありと、行基菩薩の一生杖にも柱にも此木を用給ふとかや。
世の人の見付ぬ花や軒の栗
等窮が宅を出て、五里計桧皮の宿を離れてあさか山有。路より近し。此あたり沼多し。かつみ刈比もやゝ近うなれば、いづれの草を花かつみとは云ぞと人々に尋侍れども、更知人なし。沼を尋、人に とひ、かつみかつみと尋ありきて日は山の端にかゝりぬ。二本松より右にきれて、黒塚の岩屋一見し、福崎に宿る。
あくれば、しのぶもぢ摺の石を尋て忍ぶのさとに行。遥山陰の小里に石半土に埋てあり。里の童部の来りて教ける。昔は此山の上に侍しを往来の人の麦草をあらして此石を試侍をにくみて此谷につき落せば、石の面下ざまにふしたりと云。さもあるべき事にや。
早苗とる手もとや昔しのぶ摺
月の輪のわたしを越て、瀬の上と云宿に出づ。佐藤庄司が旧跡は左の山際一里半計に有。飯塚の里 鯖野と聞て尋尋行に、丸山と云に尋あたる。是庄司の旧館なり。梺に大手の跡など人の教ゆるにまかせて泪を落し、又かたはらの古寺に一家の石碑を残す。中にも二人の嫁がしるし先哀也。女なれども かひがひしき名の世に聞えつる物かなと袂をぬらしぬ。堕涙の石碑も遠きにあらず。寺に入て茶を乞へば、爰に義経の太刀弁慶が笈をとゞめて什物とす。
笈も太刀も五月にかざれ帋幟
五月朔日の事也。
其夜飯塚にとまる。温泉あれば湯に入て宿をかるに、土坐に筵を敷てあやしき貧家也。灯もなければゐろりの火かげに寝所をまうけて臥す。夜に入て雷鳴、雨しきりに降て、臥る上よりもり、蚤蚊にせゝられて眠らず。持病さへおこりて消入計になん。短夜の 空もやうやうやう明れば、又旅立ぬ。猶夜の余波心すゝまず、馬かりて桑折の駅に出る。遥なる行末をかゝえて、斯る病覚束なしといへど、羈旅辺土の行脚、捨身無常の観念、道路にしなん、是天の命なりと気力聊とり直し路縦横に踏で伊達の大木戸をこす。
鐙摺白石の城を過、笠嶋の郡に入れば、藤中将実方の塚はいづくのほどならんと人にとへば、是より遥右に見ゆる山際の里をみのわ笠嶋と云。道祖神の社、かた見の薄今にありと教ゆ。此比の五月雨に道いとあしく、身つかれ侍れば、よそながら眺やりて過るに、蓑輪笠嶋も五月雨の折にふれたりと、
笠嶋はいづこさ月のぬかり道
岩沼に宿る。
武隈の松にこそめ覚る心地はすれ。根は土際より二木にわかれて、昔の姿うしなはずとしらる。先能因法師思ひ出、往昔むつのかみにて下りし人、此木を伐て、名取川の橋杭にせられたる事などあればにや。松は此たび跡もなしとは詠たり。代々あるは伐、あるひは植継などせしと聞に、今将千歳のかたちとゝのほひて、めでたき松のけしきになん侍し。
武隈の松みせ申せ遅桜と挙白と云ものゝ餞別したりければ、
桜より松は二木を三月越シ
名取川を渡て仙台に入。あやめふく日也。旅宿をもとめて四五日逗留す。爰に画工加衛門と云ものあり。聊心ある者と聞て知る人になる。この者年比さだかならぬ名ところを考置侍ればとて、一日案内す。宮城野の萩茂りあひて、秋の景色思ひやらるゝ。玉田よこ野つゝじが岡はあせび咲ころ也。日影ももらぬ松の林に入て爰を木の下と云とぞ。昔もかく露ふかければこそ、みさぶらひみかさとはよみたれ。薬師堂天神の御社など拝て、其日はくれぬ。猶、松嶋塩がまの所々画に書て送る。且、紺の染緒つけたる草鞋二足餞す。さればこそ風流のしれもの、爰に至りて其実を顕す。
あやめ艸足に結ん草鞋の緒
かの画図にまかせてたどり行ば、おくの細道の山際に十符の菅有。今も年々十符の菅菰を調て国守に献ずと云り。
壷碑市川村多賀城に有
つぼの石ぶみは高サ六尺餘横三尺計歟。苔を穿て文字幽也。四維国界之数里をしるす。此城、神亀元年、按察使鎮守府将軍大野朝臣東人之所置也。天平宝字六年、参議東海東山節度使、同将軍恵美朝臣獲修造而十二月朔日と有。聖武皇帝の御時に当れり。むかしよりよみ置る哥枕、おほく語傳ふといへども、山崩川落て、跡あらたまり、石は埋て土にかくれ、木は老て若木にかはれば、時移り代変じて、其跡たしかならぬ事のみを、爰に至りて疑なき千歳の記念、今眼前に古人の心を閲す。行脚の一徳、存命の悦び、羈旅の労をわすれて泪も落るばかり也。
それより野田の玉川沖の石を尋ぬ。末の松山は寺を造りて末松山といふ。 松のあひあひ皆墓はらにて、はねをかはし枝をつらぬる契の末も終はかくのごときと悲しさも増りて、塩がまの浦に入相のかねを聞。五月雨の空聊はれて、夕月夜幽に、籬が嶋もほど近し。蜑の小舟こ ぎつれて、肴わかつ声声に、つなでかなしもとよみけん心もしられて、いとゞ哀也。其夜、目盲法師の琵琶をならして奥上るりと云ものをかたる。平家にもあらず、舞にもあらず。ひなびたる調子うち上て、枕ちかうかしましけれど、さすがに辺土の遺風忘れざるものから、殊勝に覚らる。
早朝塩がまの明神に詣。国守再興せられて、宮柱ふとしく彩椽きらびやかに石の階、九仭に重り、朝日あけの玉がきをかゞやかす。かゝる道の果塵土の境まで、神霊あらたにましますこそ、吾国の風俗なれどいと貴けれ。神前に古き宝燈有。かねの戸びらの面に文治三年和泉三郎寄進と有。五百年来の俤今目の前にうかびて、そゞろに珍し。渠は勇義忠孝の士也。佳命今に至りて、したはずといふ事なし。誠人能道を勤、義を守べし。名もまた是にしたがふと云り。
日既午にちかし。船をかりて松嶋にわたる。其間二里餘、雄嶋の磯につく。
抑ことふりにたれど、松嶋は扶桑第一の好風にして、凡洞庭西湖を恥ず。東南より海を入て、江の中三里、 浙江の湖をたゝふ。嶋嶋の数を尽して、欹ものは天を指、ふすものは波に葡蔔。あるは二重にかさなり三重に畳みて、左にわかれ右につらなる。負るあり抱るあり、児孫愛すがごとし。松の緑こまやかに、枝葉汐風に吹たはめて、屈曲をのづからためたるがごとし。其景色□然として美人の顔を粧ふ。ちはや振神のむかし、大山ずみのなせるわざにや。造化の天工、いづれの人か筆をふるひ詞を尽さむ。
雄嶋が磯は地つゞきて海に出たる嶋也。雲居禅師の別室の跡、坐禅石など有。将松の木陰に 世をいとふ人も稀稀見え侍りて、落穂松笠など打けぶりたる草の庵閑に住なし、いかなる人とはしられずながら、先なつかしく立寄ほどに、月海にうつりて昼のながめ又あらたむ。江上に帰りて宿を求れば、窓をひらき二階を作て、風雲の中に旅寝するこそ、あやしきまで妙なる心地はせらるれ。
松嶋や鶴に身をかれほとゝぎす 曾良
予は口をとぢて眠らんとしていねられず。旧庵をわかるゝ時、素堂松嶋の詩あり。原安適松がうらしまの和哥を贈らる。袋を解てこよひの友とす。且杉風濁子が発句あり。
十一日、瑞岩寺に詣。当寺三十二世の昔、真壁の平四郎出家して、入唐帰朝の後開山す。其後に雲居禅師の徳化に依て、七堂甍改りて、金壁荘厳光を輝、仏土成就の大伽藍とはなれりける。彼見仏聖の寺はいづくにやとしたはる。
十二日、平和泉と心ざし、あねはの松緒だえの橋など聞傳て、人跡稀に雉兎蒭□の往かふ道、そこともわかず、終に路ふみたがえて石の巻といふ湊に出。こがね花咲とよみて奉たる金花山海上に見わたし、数百の廻船入江につどひ、人家地をあらそひて、竃の煙立つゞけたり。思ひがけず斯る所にも来れる哉と、宿からんとすれど、更に宿かす人なし。漸まどしき小家に一夜をあかして、明れば又しらぬ道まよひ行。袖のわたり尾ぶちの牧まのゝ萱はらなどよそめにみて、遥なる堤を行。心細き長沼にそふて、戸伊摩と云所に一宿して、平泉に到る。其間廿余里ほどゝおぼゆ。
三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。先高館にのぼれば、北上川南部より流るゝ大河也。衣川は和泉が城をめぐりて高館の下にて、大河に落入。康衡等が旧跡は衣が関を隔て南部口をさし堅め、夷をふせぐとみえたり。偖も義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢となる。国破れて山河あり。城春にして草青みたりと笠打敷て、時のうつるまで泪を落し侍りぬ。
夏草や兵どもが夢の跡
卯の花に兼房みゆる白毛かな 曾良
兼て耳驚したる二堂開帳す。経堂は三将の像をのこし、光堂は三代の棺を納め、三尊の仏を安置す。七宝散うせて、珠の扉風にやぶれ、金の柱霜雪に朽て、既頽廃空虚の叢と成べきを、四面新に囲て、甍を覆て風雨を凌。暫時千歳の記念とはなれり。
五月雨の降のこしてや光堂
南部道遥にみやりて、岩手の里に泊る。小黒崎みづの小嶋を過て、なるこの湯より、尿前の関にかゝりて、出羽の国に越んとす。此路旅人稀なる所なれば、関守にあやしめられて、漸として関をこす。大山をのぼつて日既暮ければ、封人の家を見かけて舎を求む。三日風雨あれて、よしなき山中に逗留す。
蚤虱馬の尿する枕もと
あるじの云、是より出羽の国に大山を隔て、道さだかならざれば、道しるべの人を頼て越べきよしを申。さらばと云て人を頼侍れば、究境の若者反脇指 をよこたえ、樫の杖を携て、我我が先に立て行。けふこそ必あやうきめにもあふべき日なれと、辛き思ひをなして後について行。あるじの云にたがはず、高山森々として一鳥声きかず、木の下闇茂りあひて夜る行がごとし。雲端につちふる心地して、 篠の中踏分踏分、水をわたり岩に蹶て、肌につめたき汗を流して、最上の庄に出づ。かの案内せしおのこの云やう、此みち必不用の事有。恙なうをくりまいらせて、仕合したりと、よろこびてわかれぬ。跡に聞てさへ胸とゞろくのみ也。
尾花沢にて清風と云者を尋ぬ。かれは富るものなれども、志いやしからず。都にも折々かよひてさすがに旅の情をも知たれば、日比 とゞめて、長途のいたはり、さまざまにもてなし侍る。
涼しさを我宿にしてねまる也
這出よかひやが下のひきの声
まゆはきを俤にして紅粉の花
蠶飼する人は古代のすがた哉 曾良
山形領に立石寺と云山寺あり。慈覚大師の開基にて、殊清閑の地也。一見すべきよし、人々のすゝむるに依て、尾花沢よりとつて返し、其間七里ばかり也。日いまだ暮ず。梺の坊に宿かり置て、山上の堂にのぼる。岩に巖を重て山とし、松柏年旧土石老て苔滑に、岩上の院々扉を閉て物の音きこえず。岸をめぐり、岩を這て仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行のみおぼゆ。
閑さや岩にしみ入蝉の声
最上川のらんと、大石田と云所に日和を待。爰に古き誹諧の種こぼれて、忘れぬ花のむかしをしたひ、芦角一声の心をやはらげ、此道にさぐりあしゝて、新古ふた道にふみまよふといへども、みちしるべする人しなければとわりなき一巻残しぬ。このたびの風流爰に至れり。
最上川はみちのくより出て、山形を水上とす。こてんはやぶさなど云おそろしき難所有。板敷山の北を流て、果は酒田の海に入。左右山覆ひ、茂みの中に船を下す。是に稲つみたるをやいな船といふならし。 白糸の瀧は青葉の隙隙に落て仙人堂岸に臨て立。水みなぎつて舟あやうし。
五月雨をあつめて早し最上川
六月三日、羽黒山に登る。図司左吉と云者を尋て、別当代会覚阿闍利に謁す。南谷の別院に舎して憐愍の情こまやかにあるじせらる。
四日、本坊にをゐて誹諧興行。
有難や雪をかほらす南谷
五日、権現に詣。当山開闢能除大師はいづれの代の人と云事をしらず。延喜式に羽州里山の神社と有。書写、黒の字を里山となせるにや。羽州黒山を中略して羽黒山と云にや。出羽といへるも鳥の毛羽を此国の貢に献ると風土記に侍とやらん。月山湯殿を合て三山とす。当寺武江東叡に属して天台止観の月明らかに、円頓融通の法の灯かゝげそひて、僧坊棟をならべ、修験行法を励し、霊山霊地の験効、人貴且恐る。繁栄長にしてめで度御山と謂つべし。
八日、月山にのぼる。木綿しめ身に引かけ、宝冠に頭を包、強力と云ものに道ひかれて、雲霧山気の中に氷雪を踏てのぼる事八里、更に日月行道の雲関に入かとあやしまれ、息絶身こゞえて頂上に□れば、日没て月顕る。笹を鋪篠を枕として、臥て明るを待。日出て雲消れば湯殿に下る。
谷の傍に鍛治小屋と云有。此国の鍛治、霊水を撰て爰に潔斉して劔を打、終月山と銘を切て世に賞せらる。彼龍泉に剣を淬とかや。干将莫耶のむかしをしたふ。道に堪能の執あさからぬ事しられたり。岩に腰かけてしばしやすらふほど、三尺ばかりなる桜のつぼみ半ばひらけるあり。ふり積雪の下に埋て、春を忘れぬ遅ざくらの花の心わりなし。炎天の梅花爰にかほるがごとし。行尊僧正の哥の哀も爰に思ひ出て、猶まさりて覚ゆ。惣而此山中の微細、行者の法式として他言する事を禁ず。仍て筆をとゞめて記さず。坊に帰れば、阿闍利の需に依て、三山順礼の句々短冊に書。
涼しさやほの三か月の羽黒山
雲の峯幾つ崩て月の山
語られぬ湯殿にぬらす袂かな
湯殿山銭ふむ道の泪かな 曾良
羽黒を立て、鶴が岡の城下、長山氏重行と云物のふの家にむかへられて、誹諧一巻有。左吉も共に送りぬ。川舟に乗て酒田の湊に下る。淵庵不玉と云医師の許を宿とす。
あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ
暑き日を海にいれたり最上川
江山水陸の風光数を尽して今象潟に方寸を責。酒田の湊より東北の方、山を越、礒を伝ひ、いさごをふみて、其際十里、日影やゝかたぶく比、汐風真砂を吹上、雨朦朧として鳥海の山かくる。闇中に莫作して、雨も又奇也とせば、雨後の晴色又頼母敷と、蜑の苫屋に膝をいれて雨の晴を待。其朝、天能霽て、朝日花やかにさし出る程に、象潟に舟をうかぶ。先能因嶋に舟をよせて、三年幽居の跡をとぶらひ、むかふの岸に舟をあがれば、花の上こぐとよまれし桜の老木、西行法師の記念をのこす。江上に御陵あり。神功后宮の御墓と云。寺を干満珠寺と云。比處に行幸ありし事いまだ聞ず。いかなる事にや。此寺の方丈に座して簾を捲ば、風景一眼の中に尽て、南に鳥海天をさゝえ、 其陰うつりて江にあり。西はむやむやの関路をかぎり、東に堤を築て秋田にかよふ道遥に、海北にかまえて浪打入る所を汐こしと云。江の縦横一里ばかり、俤松嶋にかよひて又異なり。松嶋は笑ふが如く、象潟はうらむがごとし。寂しさに悲しみをくはえて、地勢魂をなやますに似たり。
象潟や雨に西施がねぶの花
汐越や鶴はぎぬれて海涼し
祭礼
象潟や料理何くふ神祭 曾良
蜑の家や戸板を敷て夕涼 みのゝ国の商人低耳
岩上に雎鳩の巣をみる
波こえぬ契ありてやみさごの巣 曾良
酒田の余波日を重て、北陸道の雲に望、遥々のおもひ胸をいたましめて加賀の府まで百卅里と聞。鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改て、越中の国一ぶりの関に到る。此間九日、暑湿の労に神をなやまし、病おこりて事をしるさず。
文月や六日も常の夜には似ず
荒海や佐渡によこたふ天河
今日は親しらず子しらず犬もどり駒返しなど云北国一の難所を越てつかれ侍れば、枕引よせて寝たるに、一間隔て面の方に若き女の声二人計ときこゆ。年老たるおのこの声も交て物語するをきけば、越後の国新潟と云所の遊女成し。伊勢参宮するとて、此関までおのこの送りて、あすは古郷にかへす文したゝめてはかなき言伝などしやる也。白浪のよする汀に身をはふらかし、あまのこの世をあさましう下りて、定めなき契、日々の業因い かにつたなしと、物云をきくきく寝入て、あした旅立に、我々にむかひて、行衛しらぬ旅路のうさ、あまり覚束なう悲しく侍れば、見えがくれにも御跡をしたひ侍ん。衣の上の御情に大慈のめぐみをたれて結縁せさせ給へと泪を落す。不便の事には 侍れども、我々は所々にてとゞまる方おほし。只人の行にまかせて行べし。神明の加護かならず恙なかるべしと云捨て出つゝ、哀さしばらくやまざりけらし。
一家に遊女もねたり萩と月
曾良にかたれば、書とゞめ侍る。
くろべ四十八が瀬とかや、数しらぬ川をわたりて、那古と云浦に出。擔篭の藤浪は春ならずとも、初秋の哀とふべきものをと人に尋れば、是より五里いそ伝ひして、むかふの山陰にいり、蜑の苫ぶきかすかなれば、蘆の一夜の宿かすものあるまじといひをどされて、かゞの国に入。
わせの香や分入右は有磯海
卯の花山くりからが谷をこえて金沢は七月中の五日也。爰に大坂よりかよふ商人何處と云者有。それが旅宿をともにす。一笑と云ものは、此道にすける名の ほのぼの聞えて、世に知人も侍しに、去年の冬早世したりとて、其兄追善を催すに
塚も動け我泣声は秋の風
ある草庵にいざなはれて
秋涼し手毎にむけや瓜茄子
途中吟
あかあかと日は難面もあきの風
小松と云所にて
しほらしき名や小松吹萩すゝき
此所太田の神社に詣。真盛が甲錦の切あり。往昔源氏に属せし時、義朝公より給はらせ給とかや。げにも平士のものにあらず。目庇より吹返しまで、菊から草のほりもの金をちりばめ龍頭に鍬形打たり。真盛討死の後、木曾義仲願状にそへて此社にこめられ侍よし、樋口の次郎が使せし事共、まのあたり縁記にみえたり。
むざんやな甲の下のきりぎりす
山中の温泉に行ほど、白根が嶽跡にみなしてあゆむ。左の山際に観音堂あり。花山の法皇三十三所の順礼とげさせ給ひて後、大慈大悲の像を安置し給ひて那谷と名付給ふとや。那智谷組の二字をわかち侍しとぞ。奇 石さまざまに古松植ならべて、萱ぶきの小堂岩の上に造りかけて、殊勝の土地也。
石山の石より白し秋の風
温泉に浴す。其功有明に次と云。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
あるじとする物は久米之助とていまだ小童也。かれが父誹諧を好み、洛の貞室若輩のむかし爰に来りし比、風雅に辱しめられて、洛に帰て貞徳の門人となつて世にしらる。功名の後、此一村判詞の料を請ずと云。今更むかし語とはなりぬ。
曾良は腹を病て、伊勢の国長嶋と云所にゆかりあれば、先立て行に、
行行てたふれ伏とも萩の原 曾良
と書置たり。行ものゝ悲しみ残ものゝうらみ隻鳧のわかれて雲にまよふがごとし。予も又
今日よりや書付消さん笠の露
大聖持の城外、全昌寺といふ寺にとまる。猶加賀の地也。曾良も前の夜此寺に泊て、
終宵秋風聞やうらの山
と残す。一夜の隔、千里に同じ。吾も秋風を聞て衆寮に臥ば、明ぼのゝ空近う読経声すむまゝに、鐘板鳴て食堂に入。けふは越前の国へと心早卒にして、堂下に下るを若き僧ども紙硯をかゝえ、階のもとまで追来る。折節庭中の柳散れば、
庭掃て出るや寺に散柳
とりあへぬさまして草鞋ながら書捨つ。
越前の境、吉崎の入江を舟に棹して汐越の松を尋ぬ。
終宵嵐に波をはこばせて月をたれたる汐越の松 西行
此一首にて数景尽たり。もし一辧を加るものは、無用の指を立るがごとし。
丸岡天竜寺の長老古き因あれば尋ぬ。又金沢の北枝といふもの、かりそめに見送りて、此處までしたひ来る。所々の風景過さず思ひつゞけて、折節あはれなる作意など聞ゆ。今既別に望みて、
物書て扇引さく余波哉
五十丁山に入て永平寺を礼す。道元禅師の御寺也。邦機千里を避て、かゝる山陰に跡をのこし給ふも貴きゆへ有とかや。
福井は三里計なれば、夕飯したゝめて出るに、たそがれの 路たどたどし。爰に等栽と云古き隠士有。いづれの年にか江戸に来りて予を尋。遥十とせ餘り也。いかに老さらぼひて有にや、将死けるにやと人に尋侍れば、いまだ存命して そこそこと教ゆ。市中ひそかに引入て、あやしの小家に夕顔へちまのはえかゝりて、鶏頭はゝ木ゝに戸ぼそをかくす。さては此うちにこそと門を扣ば、侘しげなる女の出て、いづくよりわたり給ふ道心の御坊にや。あるじは此あたり何がしと云ものゝ方に行ぬ。もし用あらば尋給へといふ。かれが妻なるべしとしらる。むかし物がたりにこそかゝる風情は侍れと、やがて尋あひて、その家に二夜とまりて、名月はつるがのみなとにとたび立。等栽も共に送らんと裾おかしうからげて、路の枝折とうかれ立。
漸白根が嶽かくれて、比那が嵩あらはる。あさむづの橋をわたりて、玉江の蘆は穂に出にけり。鴬の関を過て湯尾峠を越れば、燧が城、かへるやまに初鴈を聞て、十四日の夕ぐれつるがの津に宿をもとむ。
その夜、月殊晴たり。あすの夜もかくあるべきにやといへば、越路の習ひ、猶明夜の陰晴はかりがたしと、あるじに酒すゝめられて、けいの明神に夜参す。仲哀天皇の御廟也。社頭神さびて、松の木の間に月のもり入たる。おまへの白砂霜を敷るがごとし。往昔遊行二世の上人、大願発起の事ありて、みづから草を刈、土石を荷ひ泥渟をかはかせて、参詣往来の煩なし。古例今にたえず。神前に真砂を荷ひ給ふ。これを遊行の砂持と申侍ると、亭主かたりける。
月清し遊行のもてる砂の上
十五日、亭主の詞にたがはず雨降。
名月や北国日和定なき
十六日、空霽たればますほの小貝ひろはんと種の濱に舟を走す。海上七里あり。天屋何某と云もの、破篭小竹筒などこまやかにしたゝめさせ、僕あまた舟にとりのせて、追風時のまに吹着ぬ。濱はわづかなる海士の小家にて侘しき法花寺あり。爰に茶を飲酒をあたゝめて、夕ぐれのわびしさ感に堪たり。
寂しさや須磨にかちたる濱の秋
波の間や小貝にまじる萩の塵
其日のあらまし、等栽に筆をとらせて寺に残す。
路通も此みなとまで出むかひて、みのゝ国へと伴ふ。駒にたすけられて、大垣の庄に入ば、曾良も伊勢より来り合、越人も馬をとばせて、如行が家に入集る。前川子荊口父子、其外したしき人々日夜とぶらひて、蘇生のものにあふがごとく、且悦び且いたはる。旅の物うさもいまだやまざるに、長月六日になれば、伊勢の遷宮おがまんと、又舟にのりて
蛤のふたみにわかれ行秋ぞ
ページ先頭へ
ホームページへ
copyright(c)2008 TENGAIYAGENHITI All rights Reserved








 平成9年(1997年)10月16日付の北國新聞・文化欄に〈芭蕉が泊まった小松の寺「立枩寺」は龍昌寺か〉という見出しで掲載されている。
平成9年(1997年)10月16日付の北國新聞・文化欄に〈芭蕉が泊まった小松の寺「立枩寺」は龍昌寺か〉という見出しで掲載されている。